〈ひと〉の現象学/鷲田精一(筑摩書房 本体1900円)

本書のオビに「この世に生まれ落ち、やがて死にゆく〈わたし〉たち、〈ひと〉として生き、交わり、すれ違うその諸相―」とある。そして「困難な時代のただ中で紡がれた、共鳴しあい連鎖する哲学的思考」とも。著者は高名な哲学者。
難解な哲学書ではないが、人生の諸相をめぐるやさしい“語り口”は基本的に哲学的だ。内容は10章に分かれ、1.顔、2.こころ、3.親しみ、4.恋、5.私的なもの、6.〈個〉、7.シヴィル、8.ワン・オブ・ゼム、9.ヒューマン、10.死、となっている。
本書の大筋は、『幼児期に〈顔〉を持って他者と遭遇する人生のはじまりから、顔の裏にあるとみえるが、顔が隠しているのではない〈こころ〉、愛や憎しみという他者との確執、家族という〈親しみ〉の磁場や、〈恋〉の情調の曲折、〈私的なもの〉や〈所有〉のしがらみ、〈個〉としての自由の隘路、〈シヴィル〉市民性の変容、〈ワン・オブ・ゼム〉と〈多様化〉のしばり、〈ヒューマン〉・そして死の意味など、人生の主題を考察したものだ。
最初のテーマ「顔」では、生後3か月たってようやく赤ちゃんが母親の笑顔に反応を示す現象を「〈顔〉との遭遇」と捉え、個の「存在の先触れ」と捉える。そしてまた顔は常に「だれかの顔」として存在するが、わたしの顔をわたしが直接みることができないといった「〈顔〉の特異性」について思考する。
そして「顔と顔の間には視線の交差が起こる。押しのけ合いや駆け引きといってもいい。顔と顔の間には、引きつけと押しのけ、粘着と引き剥がしといった、相反する力が交叉する場、いわば磁場のようなもの」が存在するという。
顔についての締めくくりは、顔の「羞じらい」を哲学したE・レヴィナスと、顔を描いては消す作業を繰り返した画家ジャコメッティの例を引いて、彼らが『終生〈顔〉にこだわり続けたのは、〈顔〉を包囲しにやってくるあらゆる意味を剥ぎとり、そして、どのような取り込みにも抵抗する〈顔〉の、脆く儚く壊れやすい、つねに〈死〉の可能性に引き渡されたその裸形の現れを、〈ひと〉という存在の原型として救い出すこと、そこにしか現在における「書くこと」の、そして「描くこと」の意味はないと信じていたからではなかろうか』と。
最終章の〈死〉では、まず、現代社会における死はシステマティックに覆い隠されているとする。ほとんどの臨終は病院の医師や機械などによって知らされる。残された人は白布に包まれた死体と面接する。死体は廃棄物のように処理される。
そこで本書は、屍体と死者について考察する。人間と死者の関係は、もはや「だれ」でもない物質としての屍体との関係ではない。過去においては、死者との関係は、いま私たちが疑うことを忘れている生体/死体、つまり効用/廃物の二分法ではなく、生者/死者/屍体という三分法だった。いいかえると、死によってこそ「死者」が誕生するのである。死者は“他”の物質ではなく“他者”として人称性を与えられる。
死はだれにでも訪れる。しかし経験することはできない。これに対して他人の死は“死なれる”というかたちで経験できる。無関係なひとの死は情報として、関係の深いひとの死は「失う」という経験、喪失の経験となる。「死なれる」という喪失感の裏には、わたしがいるのに「死なせた」という加害の思いがある。悔恨があり、苦痛がある。
「わたし」は「自分」であり、「あなた」は「他者」だが、その「他者」からみれば「わたし」が「他者」だ。死んだ「他者」には通信できないが、その死んだ「他者」も生きている「わたし」に通信をくれない。「他者」の死は、その他者からみた他者である「わたし」の死でもある。「わたしの死」について語ることは、わたしという一人称を超えて、だれかに「死なれる」という二人称の死から派生する非人称的な語りである。「わたしの死」と「わたし」がいうときには、すでに単独の、特別な〈わたし〉は“死んでいる”に等しい。
本書の、人生において〈ひと〉が遭遇し、繰り返す、“現象”“諸相”に関する根源的な考察は、哲学的思考に馴染みの薄い者にとっては、とりわけ新鮮で思わずハッとさせられる、本書のカバーデザインのように色鮮やかで 豊饒な好著である。
(山勘 2013年10月19日)
ツタンカーメン/大城道則(中公新書 2013年9月25日発行 本体800円)
1968年兵庫県生まれ 作家 関西大学大学院文学研究科史学専攻博士課程後期課程修了。バーミンガム大学大学院古代史・考古学科エジプト学専攻修了。文学博士。専攻:古代エジプト史。
現在、駒澤大学文学部歴史学科准教授。スオンジー大学歴史古典学科名誉スタッフ。
著書「古代エジプト文化の形成と拡散」「ピラミッド以前の古代エジプト文明」「ピラミッドへの道」など
はじめに
序章 ツタンカーメンとは誰か
第1章 若き王の生涯
第2章 ツタンカーメンの死の謎
第3章 女性たちの権力闘争
第4章 王の副葬品
第5章 後継者をめぐって
終章 ツタンカーメンの死の真相とは?
あとがき
カーターがツタンカーメン王墓(KV62号墓)の発掘(1922)をして、遠い過去に生きた一人の古代エジプトの王様は、世界史上もっとも有名な王様になったが、我々は彼の実像について意外なほど何も知らない。彼の黄金のマスクさえ十分な知識を持っている方は少ないだろう。マスクは≒10kg、純金製の第3の棺は110kgである。金の相場だけで考えても≒6億円で、その美術的・歴史的価値を加味したら計り知れない。一人の古代エジプト王の素顔と人生が少しでも垣間見えたという印象を読者が持つならば、という思いで執筆された(あとがき)。
世界中の誰もが知っている。それは彼が実在の人物であり、彼の墓が未盗掘で発見されていて、そこから黄金のマスクをはじめ金銀財宝が数多く出土したからだ。その上彼は少年と言える時代に即位し、19歳で死亡しているので、「悲劇の少年王」というイメージを与え、人々の関心を煽った。しかし、王墓の発見前は実在すら疑われていた無名の王であった。
彼について本当はどのくらいのことが分かっていて、あるいは何が分かりつつあるのかを専門家の立場で紹介・解説している。
彼は前1332~前1322年頃のファラオであった。一神教に転換を図り「異端の王」と言われたアクエンアテン王と(正規の王妃ネフェルトイティではなく)「若い婦人」の子である。日本ではツタンカーメンと言われるが、原音では「トゥトアンクアメン」が近い。1965年の東京国立博物館のツタンカーメン展で初めて門外不出が解かれたマスクが来日したが、その時の呼び方が一般的になった。原語の王名の意味は「アメン神の生きている像」で、当時のヒエログリフ(象形文字)では「ネブケプルウラー」と書かれているのが同一人物である。
アメン神とはもともと上エジプトのテーベで崇拝されていた地方神だが、第18王朝期に国家神となった。
彼は暗殺されたという説が実しやかに流れているが実はそうではない。現在は病気或いは怪我が大きな原因であったという説が支持されている。68年のX線検査や近年行われたDNA検査の結果である。X線検査の結果、頭蓋骨の中に小さな骨の破片があり撲殺説となったが、これは首の骨の一部であることがあとでわかった。穴はそこから脳みそを取り出したためである。
今支持されている死因はマラリア。落馬と思われる大腿骨の骨折とそこからの感染症にマラリアを併発して死亡というのが多く支持されている。
古代エジプトでは3千年以上にわたりミイラが作られたので、その数は星の数ほどある。ヘロトドスの「歴史」の中にはその作り方が詳細に述べられていて、高級品から下級品まで3段階に分かれていたそうな。彼もその1つに過ぎないが、色が黒いという。それは若くして突然亡くなりミイラに加工するときに大量の黒い樹脂で覆ったため、という。
この時代の王は絶対君主という言葉以上の権力を持って国家の長、宗教の長で後継者の任命権もあったが、後継者は先王の葬儀を行い(開口の儀)・指揮することで、王位が継承された。
父の正妻ネフェルティティは、現代エジプト人にとっての美女の代名詞で、クレオパトラを凌駕している。アンケセナーメンはこの二人の間にできた6人のうちの1人でツタンカーメンと結婚する(即ち、異母兄妹での結婚、そのせいか2人の子供は死産)。
この時代、法律や契約に基づく結婚という概念は乏しく、同棲という感覚が近いと著者は言う。但し、特定の異性とのみ関係を持つことが理想ではあった(一夫多妻はイスラムのイメージによりもたらされた誤解)。王は例外で複数の妻を持っていた。
彼の墓は王家の墓の中では最小。王の急死という事情で、宰相のアイのための墓を使ったからである。
ミイラは包帯で包まれて黄金のマスクをし、純金製の人形棺に納められたうえ金箔の人形棺、石棺、厨子や厨子覆いなど包帯を含めて11重の手厚い埋葬を施されていた。ワインやワイン壺、125本の杖など多くの埋葬品があった。
当時の平均寿命は男子が30歳代後半、女子はその前半という調査があるが、幼児死亡率が高かった時代で、80歳、90歳という王も見かける。だから、19歳の死というのはやはり早い。
王名表にはツタンカーメンを含めアクエンアテンからアイまでの王名がない。ラメセス二世が過去のファラオの名前を削り自分の名を入れたのと同様のことが、ツタンカーメンの2代あとの王ホルエムヘブがやった可能性が高いであろう。
父アクエンアテンは宗教を変え、美術様式を刷新し、遷都まで行い、エジプトのすべてを変革しようとした。ツタンカーメンは古代エジプト3千年の中でも最も激動の時代に生きた王の一人である。ツタンカーメンについて少し分かった気になった次第です。
(恵比寿っさん 2013年10月19日)
職業としての政治/マックス・ヴェーバー著・脇圭平訳(岩波書店 1980年 本体252円)
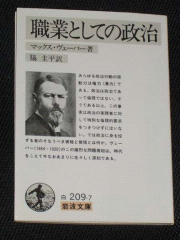 再びの政権交代で未来に少しは希望が見えたかと思ったら、税金は上がるし社会保障は下がるし景気は相変わらずで、逆に失望感が広がる今の日本である。議会制民主主義を信じてきた私たちは、民主党といい自民党といい質の悪い議員たちに政治を任せるとろくなことにならないことを思い知った(そんな議員を選んだ国民にも大いに責任はあるが)。そこで、政治家とは基本的にどんな能力と資質を備えるべきかについて改めて考えてみた。
再びの政権交代で未来に少しは希望が見えたかと思ったら、税金は上がるし社会保障は下がるし景気は相変わらずで、逆に失望感が広がる今の日本である。議会制民主主義を信じてきた私たちは、民主党といい自民党といい質の悪い議員たちに政治を任せるとろくなことにならないことを思い知った(そんな議員を選んだ国民にも大いに責任はあるが)。そこで、政治家とは基本的にどんな能力と資質を備えるべきかについて改めて考えてみた。
「すべての国家は暴力の上に成り立っている」というトロツキーの言葉の引用で始まる本書は、1919年1月、ミュンヘンでヴェーバーが学生団体のために講演した内容をまとめたものである。第一次世界大戦の戦後処理と世界の新秩序を目指すパリ講和会議が始まったばかりで、敗戦国ドイツは全土が革命前夜のような騒然とした雰囲気に包まれ、国民は自国の現状をどう認識し、再建するかが焦眉の課題だった。
ヴェーバーはこのとき55歳、社会学者として経済学者としてすでに大きな存在であり、一方で強烈なナショナリストでもあった。その彼が祖国の敗北という衝撃を共有しながらも、なぜ政治指導者たちがこの国をかくも愚かな結末に導いてしまったのか、その責任を問うと同時に、一部の前衛的知識人や学生たちがこの敗戦を「神の審判」のようにとらえ、彼らが独善的で非現実的な“革命という乱痴気騒ぎ”を始めたことを批判した。
近代国家の運営には、強力な権力(暴力)と質的、量的に十分な行政スタッフ(官僚機構)、そして行政手段が不可欠であり、権力を行使する場合の政治の倫理は当然、一般社会の倫理とは違ってくる。だから、政治家は常に事物と人間に対して距離を置いて考える必要があるが、ただし、政治の倫理はつまりは悪をなす倫理であることを痛切に肝に銘じるべきだ。つまり、彼らには特別な倫理観を持たせ、要求しなければならないと本書はいっている。
政治家に必要な資質は、「情熱」、「責任」、「判断力」であり、その情熱と判断力を駆使して情熱が仕事への奉仕として責任と結び付き、仕事に対する責任が行為の決定的な規範になったとき、初めて政治家をつくり出す。不可能に思えることに粘り強く挑戦しないようでは、およそ可能なことさえ達成できない。これはまったく正しく、あらゆる歴史上の経験がこれを証明している。
政治家を志す者は卑しい虚栄心を持ってはならず、これから自分がやり遂げようとするものに比べて自らの立場がどんなに卑屈であっても断じて挫けない人間、すべての結果に対する責任を一身に引き受け、どんな事態に直面しても「それでもなお」(dennoch)前進するといえる自信のある人間、そういう人間だけが政治家という「天職」を持つ。ヴェーバーは講演の最後にこう結んでいるが、今の日本の政治家に最も欠けているのが、残念ながらこれらの要素ではないだろうか。
本書はこんなこともいっている。戦争が国際情勢によって起こったものであれば、戦争責任を追及するようなことはせず、戦勝国に対して戦争の原因になった実質的利害を考え、戦勝国に負わされた将来に対する責任について話し合うべきだ。戦争終結で少なくとも道義的埋葬は済んでいるのに、数十年後に新しい文書が公開されるたびに品位のない悲鳴や憎悪や憤激が再燃することは不幸なことだと。何となく日本と中国、韓国の間で今論争しきりの問題を重ね合わせて、ヴェーバーの慧眼に驚くばかりだ。
ヴェーバーは「10年後にまたこの問題について話してみたい。いろいろな理由から私はどうも悪い予感がしてならない。10年後は反動の時代が始まり、諸君が期待するものはほとんど実現しないだろう」と予測したが、彼が危惧したとおり、その後ドイツにはヒトラーが登場した。およそ教養や知識とは無縁な、まったく政治家の資質を持ち合わせない人間に国家を委ねたドイツ国民は、再び悲劇を体験することになった。
今の日本は幸いなことに、議会制民主主義を存分に生かせる環境にある。歴史の悲劇を繰り返さないためにも私たちは今、「政治」の意味を、「選良」の意味を改めて考えてみる必要がある。
(本屋学問 2013年10月22日)
英雄時代の鉄道技師たち/菅建彦(山海堂 1987年4月発行 本体2,200円)
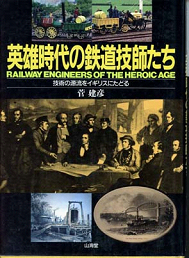
久しぶりに読みたい本に出会った。古書店でふと見掛けた本だが、手に取ると序文や目次に目を惹かれ、本文を一気に読みおえた。本書は1830年代からの約30年間、イギリスの鉄道発展を、鉄道建設、トンネル掘削、架橋などの土木技術を中心に記述した技術史である。しかし、単なる技術史に留まらず、プロジェクト推進にまつわる人間模様や政治的な駆け引きなど、興隆期のイギリス社会を生き生きと描いている。この鉄道網の普及こそ、18世紀の後半、イギリスを世界の工場にした産業革命の基盤であった。
今日イギリスの産業革命と聞くと、まずジェイムズ・ワットの蒸気機関やロバート・スティーヴンソンの蒸気機関車ロケット号などが思い浮かぶ。だがこの時代は蒸気機関の発明者ニューコメン、世界最初の蒸気機関車を作ったトレヴィシック、鉄道王ハドソン、転炉の発明者ベッセマー、鉄道・トンネル・造船に活躍した天才技師ブルネルなど、技術史上の英雄たちが輩出した時代でもあった。本書はその中からロバート・スティーヴンソンとイザムバード・ブルネルの二人を軸に物語を進めている。
ロバートの父ジョージも、鉄道の実用化に貢献し「鉄道の父」と呼ばれた。また、イザムバードの父マークも滑車や軍靴の量産機械を発明し、テムズ河に自分の発明したシールド工法で世界最初の河底トンネル掘削に挑んだ。同じ時代に二組の父子が活躍したので話が混乱する。著者は混乱を避けるため、主にスティーヴンソン家の父はジョージ、息子をロバートまたはロバート・スティーヴンソン、ブルネル家の父はマーク、息子はブルネルと記している。
第一部はスティーヴンソン父子の物語である。炭鉱労働者から身を起こしたジョージは、ストックトン、ダーリントン間に世界最初の鉄道を建設し、その後もロバートと共に鉄道建設を推進し、後年「鉄道の父」と讃えられた。ロバートが設計した蒸気機関車ロケット号は機関車試走会で優勝し、父が建設を進めた世界最初の鉄道に採用された。その後のロバートの成功と失意(落橋事故)、栄光と晩年の孤独、国葬なみの盛大な葬儀など、彼等の生涯が色彩豊かに語られている。
第二部はブルネル父子のこれまた起伏の多い生涯の物語。父マークはフランスで牧師となる教育を受けたが、途中から技師の道に転向してイギリスに渡り滑車の大量生産を始めて成功する。次に始めた軍靴自動製造工場は、当初成功したものの戦争終結で破産に終わり、辛うじて政府に救済された、その後シールド工法を発明し、世界最初のテムズ河水底トンネルの掘削に挑む。その子ブルネルはフランスで高度な工学教育を受けた。技師となってイギリスに戻ったブルネルは、トンネルを掘り、長大な吊橋を架け、超広軌鉄道の建設を推進し、世界最大の蒸気船を建造するという、まさに八面六臂の大活躍をした。父マークが途中で挫折したテムズ河トンネルを再開させ、それを完成させたのもブルネルである。ロバートと同様、彼もいくつもの成功と失敗、栄光と落胆を経験する。ブルネルが建設を推進した超広軌鉄道は技術的優位を認められながらも、最終的にはロバートの狭軌鉄道(今日では新幹線も採用した標準軌)に普及の速さで遅れをとり消えてしまう。これは後年ビデオデッキのVHS対Betaの主導権争いにも似ている。 この二人は互いに好敵手として尊敬し、ことが起こる度に助け合っているのは美しい。
実は私、狸吉も鉄道や技術の歴史の愛好家であり、イギリスで産業革命時代の技術遺産を見る機会が多かった。この本を読むと、これまであちらこちらで集めた情報が、ジグソーパズルのようにつながり実に興味深い。「あーそうだったのか!」と感動を覚えた箇所がいくつもある。「英雄」というとナポレンオンやアレクサンダー大王のような武将を思い浮かべるかもしれぬが、国語辞典で英雄とは「並みはずれた才能を発揮し、庶民のあこがれの的になると共に、そのような人の存在することが誇りに思われ、国民多数の人気を得ている人物」とある。想定外の要因による失敗。それによる信用失墜と世間の非難という危険を背に、前人未踏の技術開発に敢然と挑んだ技術者たちは、まこと「国民的英雄」と讃えられるのにふさわしい。
本書の著者はいわゆる技術屋ではなく、法学部を卒業し国鉄(現JR)で働いた文系人である。だからこそ平板な技術史に終始せず、イギリス興隆期の興奮に満ちた時代と、そこでに活躍した人々を生き生きと描写できたのであろう。技術の歴史をこのように面白く語ってくださった著者に感謝する。
(狸吉 2013年10月21日)
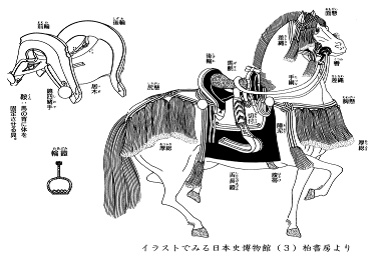 これらの記述より、天照神の前後を含めた時代であることがわかります。
これらの記述より、天照神の前後を含めた時代であることがわかります。