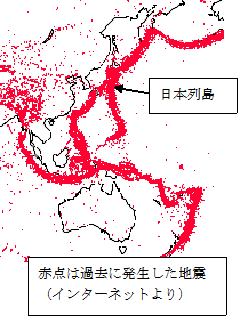経済学に何ができるか/猪木武徳(中央公論社 本体820円)
 結論的な内容を先に言えば、現実に起きている経済問題は、純粋な経済学上の問題ではありえない。経済を動かす人間は経済原理だけでは行動しない。したがって、経済学だけで経済問題は解決しない。むしろ明快な、強すぎる経済学の主張には用心すべきだと本書はいう。
結論的な内容を先に言えば、現実に起きている経済問題は、純粋な経済学上の問題ではありえない。経済を動かす人間は経済原理だけでは行動しない。したがって、経済学だけで経済問題は解決しない。むしろ明快な、強すぎる経済学の主張には用心すべきだと本書はいう。
扉には、こうある。さまざまな「価値」がぶつかり合う、現代の自由社会、その結果、数々の難問が私たちの前に立ちはだかっている。金融危機、中央銀行のあり方、格差と貧困、知的独占の功罪、自由と平等のバランス、そして人間にとって正義とは、幸福とは―。本書は、経済学の基本的な論理を解説しながら、問題の本質に迫る。これが本書の主な内容だ。
いきなりだが最終章は、本書のタイトルそのままに「経済学に何ができるか」となっている。ここでは、これまで述べてきた経済学の役割とその限界を明確にした最近の例として、TPP(環太平洋経済連携協定)への参加問題と、ユーロ危機の問題を取り上げている。
TPPでは、現在の日本にとってTPP参加は日本農業の体質見直しの刺激剤となりうるが、場合によっては打撃ともなりうる。しかし、すでにTPPに参加している国々も「全分野100%の貿易自由化」というTPPの目標がただちに達成されるとは考えていないだろう。たとえば米国が、ベトナムからの繊維輸入を関税ゼロで受け入れるだろうか。TPPは、段階的な関税の撤廃を、投資については今後の交渉に俟つ、という柔軟な枠組みで出発している。日本も産業構造を基本的に見直すチャンスとしてTPPを捉える必要がある、と本書はいう。
一方、中国はいま経済が減速し、国内の格差問題や配分問題が表面化している。同時に、軍事的な膨張は衰えを見せない。その中国が、中国を包囲するような形で近隣諸国が自由貿易圏を形成するTPPに不満と警戒感を露わにしている。TPPが中国「包囲網」だとすれば、中国は、さらに国力を誇示し軍の拡張を続けるケースも考えられる。こうした事態をいかにして回避できるか。TPPは、経済学的論理だけでは解決しない。
ユーロ問題では、「ギリシャ危機」が、ユーロという通貨が投機筋に狙われると脆弱であること、ギリシャという小国の財政破綻が世界の実体経済を揺るがすことを教えてくれた。「ユーロ」という単一通貨を、経済水準と経済構造の違うEU内の17カ国が使用することについて、本書はまず国際金融の理論を紹介した上で、ユーロ導入に無理があったと指摘する。
ヨーロッパの政治主導者たちには、長年にわたる独仏の対立を融和へと導きたい、特にフランスには、米国との対抗意識からヨーロッパの政治的統一を求めていた。共通通貨の導入はそうした「政治的な理由から」推進されたという、米国経済学者マーティン・フェルドシュタインの見解なども引用する。
単一通貨のもとで、メンバー国間に景気の大きな「格差」が生じて、経済的対立と政治的緊張が生じた場合、EUの中央銀行(ECB)はどのように統一的な金融政策を打ち出せるか。EU内の民主的な手続きで決めることはできず、結局は強い国、たとえばドイツが金融政策の主導権を握ることになるという。
TPPにしてもユーロ問題にしても、現実の政策決定は、経済的な論理と政治的な価値という相反する価値の間での選択を行わなければならない。そのためには、経済学の持つ論理の力とその限界を知り、経済の論理だけを言いつのらない品性が求められる。経済学が力を発揮できるのは、経済学の論理を用いて説得が可能な政策選択前の段階までで、それ以降は政治的な選択に任せるほかないというのが、本書の結論である。
(山勘2013年2月14日)
不況を拡大するマイナス・バブル/小山和伸(晃洋書房 2012年9月発行)
 現在の日本も世界の経済も、未来に明るい展望が無く、国家債務の肥大化と少子高齢化による年金システムの崩壊、環境問題の深刻化による経済発展の終焉、と言った共通した問題に直面している。未来に対するこうした悲観的な観測から、企業の投資も控えめとなり、それが雇用情勢にも悪影響を与えている。失業率の増大は、若い世代に悲観的な人生観をもたらし、ますます未来予測を悲観的にしている。
現在の日本も世界の経済も、未来に明るい展望が無く、国家債務の肥大化と少子高齢化による年金システムの崩壊、環境問題の深刻化による経済発展の終焉、と言った共通した問題に直面している。未来に対するこうした悲観的な観測から、企業の投資も控えめとなり、それが雇用情勢にも悪影響を与えている。失業率の増大は、若い世代に悲観的な人生観をもたらし、ますます未来予測を悲観的にしている。
こうした閉塞感の突破口として期待される技術革新さえも、福島原発の 事故以来、何かと懐疑的な視線を向けられるようになっている。悲観的予測と閉塞感の連鎖には、実際よりも誇張された不安や、実態に基づかない危惧が累積的に増殖するシナジー効果を読みとることができる。こうしたマイナスのシナジー効果は、実態以上の過大な不安や危惧感という意味において、マイナスのバブルであると言うことができる。
バブル経済の本質を、歴史的検証によって明らかにすることを通じて、われわれは人間特有の未来に対する期待や不安が、いつどのようなメカニズムで、実体的な社会から遊離してしまうのかを知ることができる。そのメカニズムを知れば、実体的社会を離れた過剰な期待や不安による弊害を、少しでも解決出来るようになるかもしれない。というはしがきで始まっています。
かつてのオランダのチューリップ・バブルなどの過去の事例や、最近でのリーマンショックについて、なるほどと分かり易く解説されています。そして、バブルに至った共通の現象を3つにまとめています。
①期待と不安を駆り立てる不確実性の存在
ある種の不確実性がつきまとい、不安材料ではあるが、投資家の期待を膨らませる。
②非専門家、素人のヤジウマ的な大量の参入
自然界には存在しない一種奇形的なチューリップが愛好家ならず投資家たちの期待を膨らませ、その球根は掘り出される何カ月も前から投機の対象となり値段をつり上げていった。
③新しい取引方法や制度、学説などの「新しい武器」と、それに乗り遅れてバカになりたくないという心理。
これが、バブルとして巨大化してゆく。地道に努力して僅かの稼ぎを得ている人が、となりがあっという間に桁違いの利益を上げているのを見て、自分がバカを見ていると思い、素人(善良な非専門家たち)がつられて参入してしまう。
それは、リスクもリターンも保証条件もまちまちな証券、債権が限りなく組み合わされ安全な高収益商品として脚光を浴び、バブル高騰となった。バブルが破たんした時、全体のお金は不変だから、多くの人は大損をした裏に、膨大な利益を得た人がいたことも改めて認識しました。
リーマンショックの時もアメリカ投資銀行の上級役員などは膨大な報酬を得ており、投資銀行が倒産した後も膨大な額の退職金を受け取っていた。バブルは多くの人から見て富を失わせるものだが、一般大衆からごく少数の特定な人々へ、極端な所得の再配分を引き起こすわけである。バブル崩壊による損失は、バブル発生による利益と相殺されており、移転されているにすぎないことを知りました。
過去の事例をもとに、東日本大震災の福島原発事故以来、いわゆる風評被害のパニックは明らかにマイナス・バブルの様相を呈していると警告されています。
それは、
①原子力や放射能汚染といった問題は、一般大衆にとって極めて不確実・不案内な事象であり、特に目に見えない放射能の健康被害に関しては、大きな不安をかき立てる要素が含まれている。
② 原子力や放射能に関して全く専門外の素人達が市販されている測定器を買いあさって、あちこちで計測を始め、国や自治体の定める基準値を超える測定結果があちこちで報告、報道され不安を拡大し続けている。
③ こうした風潮の中で、原子力や放射能の影響といった最先端技術に無知であったため、数十年後に自分や子供がガンになったという事態から逃れなければという心理から、放射能被害からの脱出の動きに乗り遅れまいとする心理に他ならない。
汚染検査が優先され、受け入れ拒否され治療を受けられず死亡した被災地域からの非難患者や、風評被害のため出荷に苦しむ農畜産業者立ちは、マイナス・バブルの被害者である。さらに、マイナス・バブルの拡大に荷担した多くの素人達は、そうでなければ手にできたはずの安全・安価な原子力エネルギーへの改善と発展の果実を、さらに世界有数の国家的技術優位という我が国の計りしれない未来の恩恵を失うことになるだろう。
著者の描く風刺画には、世界に冠たる原発技術をもつ企業がありながら、何事もなく稼働している原発をあたふたと止めて悦に入る政治家。ガイガー・カウンターや「原発反対」のプラカードを手に手にもって町中をうろつき回り、叫び声を上げる大衆。「安全」と書かれた米や野菜を川に捨てる人々…。
マイナス・バブルという概念を持つことで、警戒すべき実態以上の空騒ぎの本当のリスクを浮き彫りにすることができるのではないかと結んでいます。
私の尊敬する知人が本著者に共感したと言うことを聞き、経済には全く疎い私ですが、どんな内容か私にも理解できるかなと思い、先ずは図書館にリクエストして読んで見ました。おおよそ理解できたつもりでいます。
(ジョンレノ・ホツマ 2013年2月16日)
ぼくのオペラへの旅/黒田恭一(JTB 定価1600円)
 私の趣味の一つとしてオペラ鑑賞があります。オペラはポピュラーな芸術で、多くの人の癒しに貢献していることで知られており、日本でも高いレベルの公演が行われております。しかし、オーケストラなどは高い水準にあると思うのですが、歌手のベルに付いては、残念ながら体格のハンデもあって、見劣りしてしまうと言えましょう。その様な事情も有ると思いますが、新国立劇場では、税金で運営されている劇場でありながら、出演歌手の主役クラスは何時も外国人で占められており、専門家の中にはこれに強く抗議している方も居られます。しかし、我々ファンからするとレベルの維持にはやむを得ないし、それがなければカネを払って行く気にはならないでしょう。
私の趣味の一つとしてオペラ鑑賞があります。オペラはポピュラーな芸術で、多くの人の癒しに貢献していることで知られており、日本でも高いレベルの公演が行われております。しかし、オーケストラなどは高い水準にあると思うのですが、歌手のベルに付いては、残念ながら体格のハンデもあって、見劣りしてしまうと言えましょう。その様な事情も有ると思いますが、新国立劇場では、税金で運営されている劇場でありながら、出演歌手の主役クラスは何時も外国人で占められており、専門家の中にはこれに強く抗議している方も居られます。しかし、我々ファンからするとレベルの維持にはやむを得ないし、それがなければカネを払って行く気にはならないでしょう。
という事で、オペラファンにとって海外でのオペラ鑑賞はファンにとって夢であり、少ない費用で効率良く旅行する事を常々考えているのです。この目的にミートするのがまさしく本書であります。
本書は、音楽評論家の黒田恭一さんが、自分の経験をもとにしてオペラファンの琴線に触れる切り口でレポートしています。黒田恭一さんは、音楽評論家であり、オペラの評論を最も得意とする人で、オペラ評論家の中でもテレビやFMでの独特な語り口は、活字に変えられない親しみを覚えるものであります、しかも、音楽の専門家には珍しくオーディオマニアであられた事も私には貴重な方でした。まだまだ、活躍してもらわなければならないにも関わらず、数年前にお亡くなりなったことは残念であり、この書が貴重な存在になってきます。
さて、この書のなかで特に印象に残るところがあります。昨年、私は念願のバイロイト音楽祭に行きました、そして、ワグナーを崇拝するワグネリアン達の聖地とも言えるバイロイト祝祭劇場で、毎夜連続してワグナーのオペラ5演目を鑑賞してきました。この感激と落胆と入り混じる複雑な感傷は、私のコラムに詳しく書いてあります。この劇場を黒田恭一さんはどの様にレポートしているのか、大変興味の湧くものであります。
流石プロのお言葉です。行ってみなければ絶対にレポート出来ない内容が記されているにも関わらず、自分は行ったことが無いと記しています。これは、私の直感ですが、ワグネリアンへの気使いと読みました。バイロイトは、ワグネリアンにとって聖地であります、批判は何人であれ許されないのです。
このワグネリアンに付いて経験したことですが、我々音楽ファン、そしてオーディオマニアにとってバイロイト祝祭劇場と言うのは特別な存在であり、私が行って来た事により、先輩たちの言いようが微妙に変わってきた事などを考えると、あまり大きな声を出さない方が良いと言う事、黒田恭一さんのように行ったことが無いと言うのは絶妙な表現と思うのであります。
音楽を愛する私として、その結論は、新国立劇場のワグナー楽劇/「リング」が最高で有ったと言うこと、昨年現地を訪れ、鑑賞したバイロイト祝祭劇場の「タンホイザー」よりも、新国立劇場の今年1月の公演の方が素晴らしかったと言う事。そして、素人の私は、自由にモノが言えると言う利点を感じました。
(致智望 2013年2月16日)
AK-47世界を変えた銃/ラリー・カハナー著・小林宏明訳(学習研究社 本体2,000円 2009年4月14日 第1刷発行)
 著者はジャーナリスト。7カ国に翻訳された「競争優位の情報戦略-公開情報でここまで読めるライバルの経営戦略」をはじめ、「CULTS THAT KILL」など8冊の著書がある。ビジネスウイーク、ワシントンポスト、インタナショナルヘラルドトリビューン、クリスチャンサイエンスモニタ等にも寄稿している。また、CNNのラリーキングライブ、CBSのイブニングニュースなどのテレビ番組にも出演している。
著者はジャーナリスト。7カ国に翻訳された「競争優位の情報戦略-公開情報でここまで読めるライバルの経営戦略」をはじめ、「CULTS THAT KILL」など8冊の著書がある。ビジネスウイーク、ワシントンポスト、インタナショナルヘラルドトリビューン、クリスチャンサイエンスモニタ等にも寄稿している。また、CNNのラリーキングライブ、CBSのイブニングニュースなどのテレビ番組にも出演している。
訳者は1946年生まれ。明治大学英文学科卒。翻訳家、エッセイスト。アメリカのカウンター・カルチャー、ロック、ミステリー、犯罪ノンフィクションなど幅広いジャンルで翻訳を手がける。訳書は既に100冊を超え、主なものにサム・リーブス「長く冷たい秋」(ハヤカワ文庫)や「全米ライフル協会(NRA)監修 銃の基礎知識」など。著書には「図説世界の銃パーフェクトバイブル」等がある。
著者のノート 序文
第1章 祖国を守る
第2章 AKとM16の対決パート1
第3章 パンドラの箱
第4章 アフリカのクレジットカード
第5章 ラテンアメリカのカラシニコフ文化
第6章 アメリカを訪れたカラシニコフと彼の銃
第7章 国連も認めた本当の大量破壊兵器
第8章 AKとM16の対決パート2
第9章 AKをもう一度売り込む
エピローグ AK最後?の日
訳者あとがき
カラシニコフと言えば、誰もが知る弾倉がバナナ型をした戦闘用の自動小銃(アサルトライフル)。地域によってはとんでもなく安く買え子供でも使いこなせ、手入れをしなくても数十年はもつ。これがために世界中に普及し、1億丁もばらまかれていると言う。独立運動の武器として使われたり、紛争地域には必ず見かけたり、マフィアやギャング必携品?でどこにでもある。
これだけ普及した銃であるが、設計者のミハイル・カラシニコフは「私は自分の発明を誇りに思っている。しかし、それがテロリストたちに使われているのが悲しい。農民の助けになるような機械を発明すれば良かった。例えば芝刈り機のような」と言うように、初めはヒットラーの侵略から祖国を守るために開発されたが、制式銃に採用されたのは第2次大戦後であり、それ以降活躍?している銃である。
我々が良く知るところでは、オサマビンラディンがこれを愛用していたことであり、テロリストにとっても入手しやすい強力な戦闘用の武器である。
この銃は、50以上の正規軍の制式銃に採用され、毎年25万人以上の人々がこの銃の犠牲になっている。数カ国の国旗や紙幣に描かれている。テロリストが各地を転々と持ち歩くので、地雷よりも危険な武器と言える。もともと実用性を追求した開発されたAK-47とはアヴトマット・カラシニコフ(カラシニコフの自動銃)のソヴィエト制式採用年が47年の意味。
特徴は可動パーツが少なく弾詰まり(ジャム)が起こりにくい、熱さ、寒さ、雨、砂にも強い。恐ろしいまでの火力(600発/分)と壊れにくさはM16(米国制式銃)のように洗練された武器より勝っている。1947年にソヴィエト軍に制式採用以来8千万丁から1億丁が出回っているとされる。勿論、ソヴィエトは共産圏の国々へ何百万丁もただで与えたり製造許可したり、その後は中国などに模倣されたりしている。量産に向いていて、しかも安くできる。世界に普及しているのはそのモダン化したAKMと言われるモデルである。
ヴェトナム戦争での、出会いがしらの接近戦で、M14はAKにとても太刀打ちできないことがわかり、改良型がM16であったが、半分が故障すると言うことから、ヴェトコンは米製武器を怖がらなかったという話もある(これは米国軍の官僚主義や武器選定過程の不透明さが原因のようだ)。尤も、これは軍が開発者ユージン・ストーカーの忠告を聞かずに別の弾薬を使ったのが原因である。その故障を修理中に撃たれた例が多かった。軍の特殊部隊やCIAは極秘の任務を行うためにはAKを携行した。ヴェトナム戦争がAKライフルの名声を高め、後のアフガン紛争でその周辺地域にこのライフルを蔓延させた。その後、AK-74とか107、108などマズルブレーキを付けた反動の少ないモデルも制式になったが世界的普及品はAK-47である。
パキスタンとアフガニスタンの多くの地域で「カラシニコフ文化」がある。AKの活発な市場無くてはやって行けない、ことを揶揄? ルワンダや近隣の国では「アフリカのクレジットカ-ド」とも言われるAK。持つことが日々の暮らしに必要不可欠だからである。モザンビ-クの国旗には鍬と交差したAKライフルが描かれている。
書感
米国では銃の所有規制が長いこと叫ばれていながら、法制化の実現はこれからも遠のくような印象を受ける今日この頃ですが、もっと大掃除をしなければならないのが、世界中に散らばっているAKではないか、そんな気がしてきた1冊でした。
本文中には、AKの薬莢排出と自動装填の図解があったり、そのセレクター(セイフティ、フルオートマチック、セミオートマチック)の構造解説やその他のライフルも構造図も載せてあり、興味を引きました。これでライフルは自作出来そうですね。
ライフルは自作できても、肝心なのは銃弾で、これは自作するのは無理のようです。バナナ型の弾倉は、銃弾を横並べした時に出来る弧の形に合わせて設計されたもので、こういうところにもシンプルに作ろうと言う開発者の意図が反映されていると思います。
(恵比寿っさん 2013年2月17日)