2013年9月19日(木)午後2時~午後5時(会場:三鷹SOHOパイロットオフィス会議室、参加者:致智望、高幡童子、ジョンレノ・ホツマ、恵比寿っさん、本屋学問)
今回は、狸吉さん、山勘さんが残念ながら所用で欠席になり、いつもよりやや寂しい会になりましたが、懸案の蔵書整理に関する打ち合わせの関係で普段より1時間早く集まっていただきました。時間に余裕があった分、皆さんの発表も応答もいつものように白熱議論で盛り上がり、密度の濃い例会でした。高幡童子さん、名物の高幡まんじゅう、ごちそうさまでした。
なんとなく決まってしまった東京オリンピックですが、また公共投資ブームになるのか、既存の社会インフラの耐震補修問題、社会保障問題、そして、収束がまったく見えない原発事故問題…。景気回復のためには、増税をやる前に無能で無駄な国会議員の定数を1/10以下にするなど、構造改革をはじめ日本が根本的にやり直さなければならないことは山ほどあるかと思います。
(今月の書感)
「安倍政権で再び大国を目指す日本」(致智望)/「人間にとって成熟とは何か」(恵比寿っさん)/「日本人だけが知っている神様にほめられる生き方」(ジョンレノ・ホツマ)/「三島由紀夫の世界」(本屋学問)
(今月のネットエッセイ)
「男の帽子」(恵比寿っさん)/「バス旅行」(高幡童子)/「「おのころしま」の意味をホツマツタヱより」(ジョンレノ・ホツマ)
(事務局)
人間にとって成熟とは何か/曽野綾子(幻冬舎新書 本体760円 2013年7月30日第1刷発行)
1931年東京都生まれ、作家。聖心女子大学卒、1979年ローマ法王よりヴァチカン有功十字勲章を受章。
2003年文化功労者 日本財団会長(1995年~2005年) 1972年NGO「海外邦人宣教者活動援助後援会」を始め2012年退任。 『老いの才覚』『人間の基本』『人間関係』『人生の原則』『生きる姿勢』など著書多数。
第1話 正しいことだけをして生きることはできない
第2話 「努力でも解決できないことがある」と知る
第3話 「もっと尊敬されたい」という思いが自分も他人も不幸にする
第4話 身内を大切にい続けることが出来るか
第5話 他愛のない会話に幸せは潜んでいる
第6話 「権利を使うのは当然」とは考えない
第7話 品がある人に共通すること
第8話 「問題だらけなのが人生」とわきまえる
第9話 「自分さえよければいい」という思いが未熟な大人を作る
第10話 辛くて頑張れない時は誰にでもある
第11話 沈黙と会話を使い分ける
第12話 「うまみのある大人」は敵を作らない
第13話 存在感をはっきりさせるために服を着る
第14話 自分を見失わずにいるためには
第15話 他人を理解することはできない
第16話 甘やかされて得ることは何もない
第17話 人はどのように自分の人生を決めるのか
第18話 不純な人間の本質を理解する
早く読んで書感を作成しようという矢先に、世間を湧かせた「子供を産んだら会社を辞めなさい」という著者の発言があったので、少し頭を冷やしてからにしようと遅くなりました。
著者がそのように発言したか、真偽を調べるつもりはありません。本当のことを言うと世間からの風当たりが強い時代だからです。ここまで端的に言わなくても、それらしい気になる風景は電車内でしばしば目にします。日経新聞を抱えてスマホを手に颯爽と歩けば一人前のような顔をした女性がよく目につくからです。第20話に「教養のある女性の仕草」とか追記してくれればいいな。
内容は上記のとおりであり、一話毎に三つのサブタイトルをもって著者の言わんとしたいところを分かりやすく述べている。
特に印象的なのは第7話の次のようなくだりである。
今の時代に品などという言葉を持ち出すと笑われるだろうが、私はやはりある人を品がいいと感じる時には、間違いなくその人が成熟した人格であることも確認している。
品はまず流行を追わない。写真を撮られるときに無意識にピースサインを出したり、成人式に皆が羽織る制服のような白いショールなど身につけない。あれほど無駄で個性の無い衣服はない。それくらいなら、お母さんか叔母さんのショールを借りて身につけた方がずっと個性的でいい。有名人に会いたがったり、サインをもらいたがったりすることもない。そんなものは自分の教養とは全く無関係だからだ。
品は、群れようとする心境を自分に許さない。自分が尊敬する人、会って楽しい人を自分で選んで付き合うのが原則だが、それはお互いの人生で独自の好みを持つ人々と理解しあった上で付き合うのだ。単に知り合いだというのは格好がいいとか、その人と一緒だと得なことがあるとか言うことで付き合うものではない。その意味で、最近流行りのフェイスブックなどというものを信じる気にはならない。
品を保つということは、一人で一生を戦うことなのだろう。それは別にお高くとまる態度を取るということではない。自分を失わずに、誰とでも穏やかに心を開いて会話ができ、相手と同感するところと、拒否すべき点とを明確に見極め、その中にあって決してながされないことである。
この姿勢を保つには、その人自身が、川の流れに立つ杭のようでなければならない。この比喩は決して素敵な光景ではないのだが、私は川の中の杭という存在に深い尊敬を持っているのである。
(恵比寿っさん 2013年8月30日)
日本人だけが知っている神様にほめられる生き方/岡本彰夫(幻冬舎 本体952円 2013年6月発行)
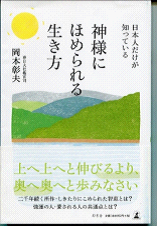 著者は春日大社権宮司です。帯表紙に、「順風満帆な人生は仕上がりが悪い。失敗の多い人生こそ、気づきがあり、人の言葉も身に沁みます。人生に迷ったとき、もうこれ以上歩めないと思ったとき、この本を手に取ってもらい、生きるよすがにしていただければと念じています。」とあるように、どのページを開いても、人生訓が簡単明瞭に書かれています。ちょっとふり返りたいと思ったときに読み直したいと思った次第です。
著者は春日大社権宮司です。帯表紙に、「順風満帆な人生は仕上がりが悪い。失敗の多い人生こそ、気づきがあり、人の言葉も身に沁みます。人生に迷ったとき、もうこれ以上歩めないと思ったとき、この本を手に取ってもらい、生きるよすがにしていただければと念じています。」とあるように、どのページを開いても、人生訓が簡単明瞭に書かれています。ちょっとふり返りたいと思ったときに読み直したいと思った次第です。
以下、抜粋いたします。
第一章 目に見えぬものこそが大切
大自然の力を借り、節目のある生活をする。
何千年の知恵を凝縮した「習わし」が心を豊かにする。
周りの人をほめてあげよう。そして、たまには自分もほめてみよう。(口癖が人生を変える)
打算のない行動が運命を開く。
神仏を敬う気持ちが、人を謙虚にさせる。
一生懸命苦しい坂道を上った人にだけ、神様は「ここにいるぞ」と教えてくださる。
第二章 必ず幸せになる秘訣
失敗してもなお、望みを捨てない。
生きては認められ、死しては人に語り継がれるような人生ほど幸せなものはない。
最悪の場合を想定し、「構えずして構える」。
腑に落ちなければ、身につかない。(体験してこそ、自分の力になる)
軽きは軽きにかえり、重きは重きにかえる。(行動は謙虚に、目標は高く持つ)
言葉はすぎるべからず。
世の中に不必要なものなどない。すべてに存在する理由がある。(寄り道が余裕のある生き方を教えてくれる)
死と向き合い、いのちの尊厳、死の尊さを心に刻む。(人生の着地点を見据え、準備を怠らない)
第三章 誇りを取り戻す
誇りを持つと自信がわいてくる。
「当たり前のこと」を深く追及する。どんな仕事でも誇り・向上心・真心の三つが大切。当たり前のことをやり続けることで、知恵と技が身についていく。
職人技は日本の誇り。その「知恵」と「技」を絶やさない工夫をする。
極端に走ってはダメ。両方の均衡をとり、折り合いをつける。
少々のことでは動じない、深い心を持った人間になる。(能ある鷹は爪を隠す)
一所懸命取り組んだものには強い力が宿る。
技の伝承は「人造り」。
第四章 男というもの、女というもの
心と心が一つになることこそ結婚。(粘り強いのは女、許容するのは男)
いのちや知恵、伝統を伝えるのは女性。仕事を全うし、家族を守るのは男性。
すべてを知ったうえで、尊敬し合える間柄になろう。
父は威厳のある存在であれ。それを支えるのが母の愛情。
この世で起きたことは、必ずこの世で解決できる。(嫁姑問題を解決するのは夫の技量)
知恵の出盛りは七十過ぎ。(根が丈夫であれば、枝は枯れることはない)
第五章 神様に愛でられる人生
感謝の気持ちは幸せへの入り口。
上へ上へと伸びるより、奥へ奥へと歩みを進める。
学校では教えてくれない人情の機微が、社会に出たときに一番大切。(相手を思いやる心を学ぶ)
死ぬまで必要とされる人生を歩む。(人のために生きる)
(ジョンレノ・ホツマ 2013年9月13日)
安倍政権で再び大国を目指す日本/屋山太郎(海竜社)
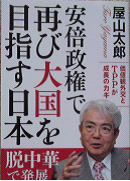 これから暫くは、好き嫌いはあるものの、選挙で信任された政権故に暫くはお付き合いしなければならない安倍政権だ。本書は、安倍政権の応援賛歌的な内容を覚悟して読み始めたのだが、それがどうして、初めから自民党批判で思いもよらない内容に読み急ぐ結果になった。
これから暫くは、好き嫌いはあるものの、選挙で信任された政権故に暫くはお付き合いしなければならない安倍政権だ。本書は、安倍政権の応援賛歌的な内容を覚悟して読み始めたのだが、それがどうして、初めから自民党批判で思いもよらない内容に読み急ぐ結果になった。
自民党の功罪、特に罪は許しがたいと言う。財政赤字を積み上げた事、原発推進の先導役を演じた事、官僚主導政治を定着させた事、その弊害の代表例が、昭和のバカ査定の一つ瀬戸内海に3つの橋をかけた事に代表する例を挙げてこき下ろしている。
一方の民主党は、「やらない」と公約した増税を財務省に恫喝され、当時の谷垣総裁と一緒に呼びつけられて実現したと言うから、その恫喝ぶりは想像を絶する。こう考えると、日本国は民主党のスローガンを実行する以前の政治環境であり、たとえ国民の信任を得た政党と言えども、未熟な手腕では官僚主導の実態を崩すことは出来ないと言わなければならない。
著者は、このような状況を作ったのも自民党と言っている。しかし、その自民党も小泉さんの「ぶっ壊し」政策で変わってきていると言う、特に安倍さんは小泉さんの意思をついだ政治家であり、これからの行動が期待できると言うのが本書の趣旨であった。
本書の内容には、我々の知らない事実関係が記されており面白く読み進んだのであるが、自民党も一つ思想で固まっているわけではない、油断すると傀儡の自民党魂がお化けのように出てきても不思議でない状況にあると言う。
本書に記された、事実関係には「ゾっ」とするものがあり、特に既得権層の健啖ぶりは、この国の将来に大きな障害を齎すと思う。米国にも「銃」の問題など既得権層の存在に付いて言われるが、日本の場合は精神構造にまで至る重症の様に思えてならない。
中国に付いても、この国はどうにもならない事は既に明らかで、為政者が日本たたきをしないと国が持たない状況に至っていると言う、その事実関係に付いて具体例を上げて解説している、結論として、この国との関係を絶つべきと言い切っている。
安部さんが進めようとしている3本の矢が成功するには、規制緩和、地方分権など、その障害となる官僚主導政治からどう脱却するかがカギと言う。折角の長期政権である、憲法改正や国のあり方に至る骨幹にまつわる問題を解決して貰いたいものだと思う。
読み進んで行くと、何か民主党と同じことを言っている様に聞こえる。だとすれば、力のあるものに頼った方が良い事になるが、この際、党派に拘り無く「志」を同じくする者同士が集まって改革を勧めれば良いと思うのであるが、それには、我々がまだまだ知らない事実が有るのかも知れない、勉強不足の民を抱えた民主主義のあり方も難しいものだ。
アベノミクスの最大の論点である「金融政策」に付いては、本書にて触れる箇所は少ない。それは著者の専門外のためと思われるが、その点の詳細は浜矩子氏の著書に詳細に記されているので、次回にその書感を述べたい。
(致智望 2013年9月6日)
 フランス文学者で評論家でもあった著者の村松剛(たけし)は、立教大学や筑波大学などで教鞭を取り、マスコミにもよく登場した保守派の論客として知られるが、母親が三島由紀夫(本名・平岡公威(きみたけ)。明治政府の技術官僚で日本の近代工学、土木工学の先駆者といわれた、祖父が尊敬する古市公威(こうい)から名付けたといわれる)の母、倭文重(しずえ)とは子供のときから知り合いで、その後もお互い家庭裁判所の調停委員を務めるなど平岡家とは親交があった。
フランス文学者で評論家でもあった著者の村松剛(たけし)は、立教大学や筑波大学などで教鞭を取り、マスコミにもよく登場した保守派の論客として知られるが、母親が三島由紀夫(本名・平岡公威(きみたけ)。明治政府の技術官僚で日本の近代工学、土木工学の先駆者といわれた、祖父が尊敬する古市公威(こうい)から名付けたといわれる)の母、倭文重(しずえ)とは子供のときから知り合いで、その後もお互い家庭裁判所の調停委員を務めるなど平岡家とは親交があった。
三島は1925年、村松は1929年生まれと年齢も近く、妹で女優の村松英子が一時期、三島が主宰する劇団の団員だったことや、三島が45歳の最後の誕生日を著者の家で過ごしたなどのエピソードからも、著者は三島を最もよく知る1人であったといえる。
1970年11月25日の三島の自決後、彼の出自をはじめ家系や血筋、果ては同性愛説や右翼説まで、まったく見当違いの解説や妄想に近いさまざまな三島伝説が巷間に流布した。たとえば、野坂昭如が三島の父方の祖母、夏子の少女時代の有栖川宮威仁親王との悲恋を書いているそうだが、客観的な資料からまったくの空想と著者は断じている。また、同性愛心中説が流れると、一部週刊誌からその痕跡が解剖で発見されたか警察に問合わせがあり、担当者の失笑を買ったそうだ。
事件から10年後、著者は堤清二(辻井喬)から、そうした伝説にとらわれない三島像を書くよう勧められる。しかし、彼の最も身近にいた著者は、そのあまりの衝撃の大きさから最初は三島の著作を読むことさえ辛く、彼の死の衝撃を受け入れ、心の動揺を収めて整理するまでさらに長い時間が必要だったと書いている。帯に「衝撃の死から20年、誤解や曲解に基づくさまざまな<三島伝説>を払拭する本格評伝」とあるように、著者は改めて冷静な気持で彼の作品を読み返し、周到に準備していた資料を活用して、1988年から1990年まで21回にわたり雑誌「新潮」に連載したものが本書となった。
著者は、できるだけ作者自身の言葉による伝記という形式を取ったと書いている。独断を避け、三島の創作や評論、日記などを通じてその生涯を浮かび上がらせるように努め、改めて主要な小説、戯曲、評論のほとんどに触れたという。
序章では三島の生家や祖父母について詳しく書いているが、苦学して東京帝国大学を卒業後、内務官僚として原敬に引き立てられ、福島県知事から樺太庁長官を務めた祖父の平岡定太郎、控訴院判事を父に持ち、ある時期は有栖川宮家に預けられて優雅な少女時代を送った祖母の夏子のことを、三島は「祖父の事業欲と祖母の病気と浪費癖が一家の悩みの種だった」と『仮面の告白』で書いた。著者も、後年は疑獄事件で没落した祖父が事業を起こしては借金を重ねた平岡家の生活の浮沈が、幼少期からの三島の精神形成に大きく影響したと分析している。
すでに精神的、肉体的病を得ていた夏子は、息子の梓と倭文重との間に生まれた初孫の三島を、2階で育てるのは危険という理由で生後49日目から手許に独占して溺愛し、授乳以外は母の倭文重にすら会わせようとしなかったそうだ。著者の表現を借りれば、“まさに不条理に祖母の病室に閉じ込められていた”のである。著者の母が倭文重から離婚したいという話をよく聞かされたのも、すでにこの頃からだったのかもしれない。
近所の男の子と遊ぶことは禁じられ、遊び相手は祖母が選んだ3人の女子だけという異様な生活環境が、幼少期の心身に影響を与えないはずがない。それは、夏子が進路まで決めたという学習院中等科時代まで続いた。ここでも三島は、「13歳の私には、60歳の深情の恋人がいたのであった」と書いている(『仮面の告白』)。神経質な、過保護に育てられた児童に多いといわれる「自家中毒」に、三島も長く苦しめられたようである。後年、著者が同じ病気の経験者と知って三島が「あれくらい人生の不条理を感じさせる病気はないねえ」としみじみ語ったとき、著者は“人生の不条理”という強い語句がとくに印象に残り、“同病相憐れむ”以上の彼の感情の吐露を感じたという。
三島が死んだ直後、母の倭文重が著者に「学習院中等科終了のときに一高を受験させたが、もし一高のバンカラ生活を経験させていたら、公威もあんなことはしなかったと思う」と語ったそうだ。その当時、三島が友人に宛てた手紙によれば、彼はこの重要な時期に受験の準備ではなく“小説の書き直しなど”をしていたという。もちろん不合格だったが、三島にとってはまさに面目躍如のエピソードではなかったか。
高名な漢学者を父に持つ母が我が子に示した理解と愛情に対して、やはり東京帝国大学を出て農林省水産局長まで務めた父の平岡梓は、少年の三島が徹夜で書いた小説を「この不良少年が」と目の前で原稿を破り捨て、息子の夢を平気で打ち砕くような人物であり、子供の教育に関しても妻にまったく無理解な夫であったと本書は明かしている。
また、本書に“K子嬢”として登場する三島の初恋の人であり、婚約寸前までいった女性の存在も、その後の三島の文学や精神構造に投影されたと著者はみている。10代から20代の多感な時期に美しい恋の対象であったK子嬢は、彼がはっきりと意思表示をしなかったためか、三島よりだいぶ年上の銀行員と婚約し、結婚してしまう。その初恋と破局が、三島の生涯と作品に及ぼした影は大きかったといわざるを得ないと著者はいい、そうした心の傷を癒しながら三島は自己改造に挑んだのである。
著者が三島と個人的に親しく付き合い始めたのは昭和30年代半ば以降というが、三島の私生活が母を通じて著者の耳に入るようになり、三島の少年時代に触れた文章を著者が書いたとき、三島は露骨に不愉快そうな顔をして「よそうよ、ああいうことを書くのは。お互いに尻尾は握っているのだから」といったという。それ以来、三島の生立ちについて一切触れないようにして、雑誌に連載中もその言葉と三島の表情が何度も思い出されたと著者は述懐している。
イギリスやスウェーデン、ノルウェーなどの民兵組織に倣った自衛隊を補完する国の民兵として、三島の民兵隊構想は1967年頃から始まり、最初は「国土防衛隊」と名付けたが「祖国防衛隊」と変わり、財界に絶望して資金援助を仰ぐことを止めた三島は、自衛隊にも政治家にも愛想を尽かし、自ら「楯の会」をつくった。この会に佐藤栄作首相が資金援助を申し出た話(三島もさすがにこの申し出は辞退している)は、事件後もしばらくは明らかにできなかった。
ヴェトナム戦争に反対して首相官邸前で焼身自殺した若者の行動に感銘を受けた三島は、「政治的行動はああでなければ」「人間はファナティック(狂信的)な面がなければ駄目だ」と意味深長な発言をした。議会制民主主義の支持者だったという三島が、「昭和45年の安保騒動は、俺が斬死にする」と高笑いとともに著者にいうようになったのは、著者の知る限り1967年秋からだったという。
三島が1970年の7月に新聞に寄せた最後の論文「果たし得ていない約束」について、三島文体の特色である逆説や諧謔は影もなく、そのあまりに投遣りで苛立たしげな文体に驚き、ほとんど日本社会への縁切り状と見たと著者は書いている。三島は決行前の夏には『豊饒の海』4部作(「春の雪」「奔馬」「暁の寺」「天人五衰」)の最終稿「天人五衰」をすでに書き上げ、出版社に渡していたという。
決行の日、著者は香港にいたが、マスコミからの知らせに「とうとうやってしまいましたか」といった以外、何を話したか覚えていないという。しかし、著者自身、三島がここまで行動することを想定できていたのだろうか。
川端康成が葬儀委員長を務めた三島由紀夫の本葬は、1971年1月に築地本願寺で営まれ、三島が予言していたとおり、佐藤首相は事件後に「天才と狂人は紙一重」といった。それを気にしていた寛子夫人はどうしても葬儀に出たいといったが、警備上の理由で実現しなかった。気丈な母は棺に向かって「公威さん、さようなら」と小声で送ったが、本当は「公威さん、立派でしたよ」と大声でいいたかったのだと後になって語っている。
三島の『葉隠入門』には、「武士道というは死ぬことと見つけたり」として“死の尊厳”が示されている。平和と繁栄のぬるま湯に浸っていた日本社会全体に、血に染まる白刃を突き付けた三島が死を賭して訴えたかったものを、現代の私たちはどこまで理解できるのか、あるいは理解しようとしているのか。そして、三島が描いた日本という国家のかたちとは、一体どのようなものだったのだろうか。
(本屋学問 2013年9月15日)