2015年1月21日(水)午後3時〜午後5時(会場:三鷹SOHOパイロットオフィス会議室、参加者:狸吉、致智望、山勘、高幡童子、恵比寿っさん、ジョンレノ・ホツマ、本屋学問)
2015年第一回の例会は、皆さん元気に打ち揃いました。偶然か、日本と韓国の国家問題に関する本の紹介がほとんどで、はからずも皆さんの関心の高さが現われました。日本はどこへ行くのか? 一番知りたいのは、我々日本国民です。新たな年を迎えて、一層盛んな投稿をよろしくお願いいたします。
山勘、狸吉両ご令室を迎えた新年会は、さらに盛り上がりました。蕎麦も美味でし。いつもながら、恵比寿っさんのご尽力に感謝感激です。
(今月の書感)
「人間年輪学入門―熟年・高年―」(狸吉)/「新・戦争論」(致智望)/「日本劣化論」(本屋学問)/「だから日本はズレている」(ジョンレノ・ホツマ)/「悲しい歴史の国の韓国人」(山勘)/「韓国人による沈韓論」(恵比寿っさん)
(事務局)
人間年輪学入門 - 熟年・高年 - 宮城音弥著 (岩波新書1982年 本体430円)

著者は戦後間もない頃フランスで心理学・精神医学を学び、帰国後いくつかの大学講師を務め、その後、東工大教授として学生たちに心理学を教えた。私(狸吉)もその中の一人として生前講義を拝聴したことを思い出し、図書館でふと目にした本書を読み始めた次第。
表題の通り、この本はまず熟年期(45〜65歳)の特性を解明し、次いで高年期に移行する過程や 移行後の問題、その対応策などを論じている。
熟年期とは人間の動物的・肉体的能力が衰え、人間的・精神的な能力が発揮される、いわば第二の人生である。熟年の思考能力は経験により強化され、複雑な問題の判断や処理に「年の功」を存分に発揮する。
熟年期から高年期に向かうと、記憶力の減退などに加え、定年・家族との別れ・経済的破綻などに遭遇し、それをきっかけにうつ状態に陥ることがある。脳の病的変化による性格変化、今日の認知症などもある。高齢者の性格は千差万別であるが、高齢者に共通した性格的特徴は、「自己中心性・家族中心性・子どもの世界への退行」であり、これらはみな同じ傾向の別の側面である。すなわち、社会的活動から離れると、身の回りの狭い範囲だけに目が行き、自然にそのようになるのだ。
本書は「高年の性・高年の生きがい」にかなりのページを割いている。高齢者は単純に枯れ果てて行くのではない。配偶者を失った高齢者同士の再婚は少なくない。再婚の理由として男性の3/4、女性の2/3近くが、「寂しかった。自分を必要とする人と生活を共にしたかった」と述べている。 しかし、著者は「高齢の親の結婚に対して子どもが不快と感じたり、反感を抱いたりすることがあり、遺産相続が絡んでくることも無視できないであろう」と述べている。これはこの拙文を綴っている狸吉自身や、同世代の友人・知人に実例が多々あり、著者の洞察力に感嘆した。
著者は「高齢者の筋力の衰えはロボットで、視力・聴力の低下も機器で補うことができる。思考力や選択力の速度低下も気にすることはない。長年の経験を活用すれば、若い世代よりも優れた選択や判断ができる」と論じ、高齢まで労働は続けられると主張している。また「今日の高齢者保護は精神衛生上は、かならずしも保護になっていない」と断じ、「適当な労働は人間を長生きさせ、生きがいを与える」、「人間の心と体は使いすぎて老化するのではない」と説く。
最後に、イギリスのことわざ「さびつくより、すれきれるほうがまし It is better to wear out than to rust out」は常に真理と結んでいる。狸吉も深く共感した。
本書が刊行された80年代初頭は、日本の人口はまだ増加中で、人々がやっと高齢化問題に気付いた時期であった。この時点で数十年先の社会的問題を予測し、かつその解決策まで提示しているのは流石である。諸問題が現実化した今日、本書は再読されるべきであろう。
(狸吉 2015年1月8日)
新・戦争論/池上 彰・佐藤 優(文芸春秋)
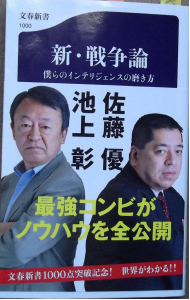 本書は、佐藤優と池上彰の対談形式によるもので、最近の時事問題をインテリジェンスの側面から捉えて述べている。
本書は、佐藤優と池上彰の対談形式によるもので、最近の時事問題をインテリジェンスの側面から捉えて述べている。
その題材は、現代に生きる我々日本人にとって最大限に興味のある話題であり、どれをとってもその題材は、一つとして見逃す事の出来ないものである。そして、その内容は、真実を知らされると言う事以上に新聞紙上には現れない、インテリジェンスと言う特殊な切り口から述べられており、書感として書くに当たり割愛するところが無い。私如きが感じを述べるなど、とてもおこがましい内容の数々なのである。
佐藤優の紹介は割愛する。氏は歴史認識から問題の原点をつかみ、その解説、説得力はすでに広く知られている。池上彰も最近の朝日新聞社の誤報事件の発端をなすジャーナリストとして知られ、その情報量は膨大なものに思える。氏は、NHKの記者、キャスターを歴任して、現在東京工業大学の教授で著書には「池上彰のニュースから未来が見える」など多数ある。
本書の何処をとっても重要なのであるが、私が目から鱗として感じた事は、ウクライナ問題であった。ウクライナは、ヨーロッパとしてみると極めて田舎の存在で、ウクライナと言う語意も田舎と言う意味だそうだ。この国は、過去からまともに相手にされない存在であり、特にナチドイツ・の時代は、ナチに肩入れし相当に悪さを働き、その地域が現在の親ヨーロッパ地区と言われている。
この地域は、過去より鼻つまみ者の扱いを受けて来た地域と言う。また、クリミアはもともとロシアが統治していた地域で、それが一つの国として独立したから、現代に至ってもロシアは進出すべく、ちょっかいを出し続けており、今更問題が生じた訳では無いのだが、やり方があまりに露骨すぎると言う事で、大きな国際問題になったと言う。何れは問題が起こるであろうと予測される地域であったと言う。だから、ヨーロッパも何か歯切れが悪い、アメリカはどこか力が入らない。しかし、ロシアのやり方を許すと、対中国への牽制も利かなくなり、許す訳には行かないと言うのが実態との事。日本も程ほどに付き合うべきで、やっと最近その方向を理解するようになって来たと言う。
今、地球上で戦争が絶えない地域は、益々おお事になるであろうとの事、過去のヨーロッパの様に戦争に明け暮れて、人を殺し過ぎた、その反動から平和を求めるようになったのが実態。いま殺し合いをしている所は、まだ殺し足りないから、平和を求める気になれないでいると言う。この2人の論客は、極めて、冷酷な見方をしている。この様にみると、如何すれば良いか、解答はおのずと見えてくる気がするが、当事者の事を考えると穏やかでない。
その他、イスラム国の問題、日本人に気が付かない朝鮮問題、中国から尖閣を守る方法、弱いオバマと分裂するアメリカ、などなど、気になるテーマが満載。オバマは教養が邪魔して前任のブッシュの様に即断即決が出来ない、だから弱腰と言われる、それが良いのか、悪いのか、この2人の論客の対談に目が離せない。
(致智望 2015年1月10日)
 何とも刺激的なタイトルだが、ある程度の社会意識を持つ人なら、最近の日本がいろいろな面で明らかに劣化していることは実感している。本書は、「日本の保守はいかに劣化しているか」、「日本の砦、アメリカと天皇」、「アジアで孤立する日本」、「右と左がどちらも軟弱になる理由」、「反知性主義の源流」、「独立という思想へ」からなる各テーマを、学生運動を経験した1948生まれの作家と、1977年生まれの気鋭の政治学者が対談する形式で論じたものである。
何とも刺激的なタイトルだが、ある程度の社会意識を持つ人なら、最近の日本がいろいろな面で明らかに劣化していることは実感している。本書は、「日本の保守はいかに劣化しているか」、「日本の砦、アメリカと天皇」、「アジアで孤立する日本」、「右と左がどちらも軟弱になる理由」、「反知性主義の源流」、「独立という思想へ」からなる各テーマを、学生運動を経験した1948生まれの作家と、1977年生まれの気鋭の政治学者が対談する形式で論じたものである。
著者らの結び付きは、今や人類最悪の核事故になった福島原発事故を、ある意味で日本近代化の必然的な帰結と考える共通認識から始まったそうだ。つまり、未曾有の大地震、大津波の結果とはいえ、防ぎ得た大惨事を現実のものとしてしまったことは、大東亜戦争の失敗を反省することが戦後であったはずなのに、相変わらず“加害者意識”の希薄な外交政策を取り続け、中国や韓国との関係をさらに悪化させてしまったことはもちろん、今や同盟国であるアメリカとの関係さえ危うくしている日本という国家の怠慢、鈍感さと同じだという。
本書によれば、19世紀は国民戦争、20世紀は世界戦争、21世紀は世界内乱という国際戦争の流れのなかで、20世紀の戦争はデスマッチであることに無自覚だった日本は(この認識は後知恵だとしても)安易に対米戦争に踏み切り、一敗地に塗れた。敗戦後の日本がアメリカの影響下で形成してきた国家のさまざまな形式や制度を「戦後レジーム」といい、「日本国憲法を頂点とした行政システム、教育、経済、雇用、国と地方の関係、外交・安全保障などの基本的枠組み」と定義されるそうだが、自主憲法の制定を党是とする自由民主党と安倍政権がやろうとしているこの「戦後レジーム」からの脱却と日本の将来について、著者らはその方向と方法の危うさをそれぞれの考えや思いを持って討論している。
もちろん、著者らは政治外交や経済問題の専門家ではないので、国際政治、地政外交、軍事、経済など現実の困難な問題に対して具体的な提言はない。そんな有効な方策があれば、賢明な政治家ならとっくに採用しているだろう。しかし、“岡目八目”という言葉もあるように、専門家が見落としてきた事象について違った観点から思索した現状認識と、そんな見方があるのかと思い知らされる部分はある。
70年近く経っても実質的にアメリカの支配から脱却できない日本の基本的枠組みが、冷戦後の世界情勢の変化に対応できなくなったことから、安倍政権は憲法改正を始め大胆な構造改革を行ない、完全な独立国家としての未来を目指しているが実際はその反対で、著者らが唱える「永続敗戦レジーム」の純化だという。それは、戦前戦後の悪い本質部分だけをより純粋な形にする、つまり、歴史的修正主義や幼稚きわまる軍事への傾斜など、これまでは日本国内のイデオロギー的右傾化を黙認し修正主義を認めてきたアメリカ自身が変化したこと、さらにアメリカが国連中心主義を捨て、日米間で安全保障より根の深い文明の衝突という問題が絡み、また冷戦終結以降、教科書や靖国問題に敏感に応じ始めた中国や韓国の動きのように世界構造自体が変動していることに安倍は無自覚だという。
本書のキーワードは “反知性主義”。つまり、社会を構成する各階層の知的レベルが低下した結果、政治家もマスコミも官僚も国民もすっかり馬鹿になって、今後さらに複雑さと困難さを増す国家運営や対外政策を果たしてうまくやっていけるのかという懸念が、本書の最大のテーマであり、切口でもある。
その好例が、インターネットに蔓延る“ネット右翼”いわゆる「ネトウヨ」現象である。彼らは基本的に無知で文献を読まないし、参照もしない。偏狭な自分の意見以外受け入れず、論破されても同じことをいう。彼らに理解できる言葉があるかはわからないが、安倍首相も反知性主義のネトウヨ同然だといい、日本の最近の右傾化、劣化はどうもそれに近いものがあるのではないか。社会全体に反知性主義が広がり、政治構造の劣化が進み永続敗戦レジームが続くなかで日本人が成熟するわけがないと本書はいう。
ある防衛庁(当時)キャリアの話が面白い。ソ連が崩壊して最大の仮想敵国がなくなり、冷戦後についてのレポートを書けといわれ、「今後の仮想敵国はアメリカ」と書いたら首になったそうだ。この話は日本の官僚機構の駄目さ加減を象徴していて、国家というものはあらゆる可能性を考えなければならず、そんな人材こそ残しておくべきだ、しかも1990年代初頭にそんな大胆な発想をしたのは先駆的だと本書はいい、そうした単純な国家意識が永続敗戦レジームを惰性で続けていく傾向をつくり出していると厳しい。
丸山真男によれば、戦前の日本には大衆と知識人の中間にいわば町内会の世話役的な中間層が存在したそうで、彼らが日本のファシズムを支えた。一般大衆は啓蒙や知性に関心がなく、そんな世界も知らない。軍隊でいえば半インテリの下士官クラス、町会の世話役といった中間層が知識層に反感を抱き、反知性主義に流れていった。だから、反知性主義は教養や知性の対立軸にはなく、その裏返しあるいは劣化したものらしい。
自民党には無知蒙昧な反近代主義者やウルトラ精神主義者政治家がいて、彼らの後援会は町内会の世話役連中なので、南京虐殺はなかったとか靖国を参拝して何が悪いといった本音が出る。政治家が下士官レベルに落ちぶれたのか、あるいは最初から下士官クラスが政治家になったのか。フランスでもジスカールデスタンからシラクまでは教養人を演じていたが、サルコジになると一気にレベルが下がったと本書は表現しているが、確かにうまい表現かもしれない。日本にも読み書きの怪しい総理がいた。
また、元・早稲田大学総長の話として、当時の大学当局が核マル派など新左翼セクトに金を渡して大学を見張らせ、キャンパスに共産党が浸透するのを阻止したという話が紹介されているが、こんなエピソードも随所にあって、単なる対談を超えたリアルさもいい。
かつてキッシンジャーが周恩来と会談したとき、在日米軍の意味を「日本の軍事化に蓋をする」といったらしいが、こんなアメリカとしたたかに付き合っていくには、今こそ日本は現実を直視して再び知性主義を取り戻す必要があり、思考停止している時間はないのではないか。
(本屋学問 2015年1月13日)
だから日本はズレている/古市憲寿(新潮新書)
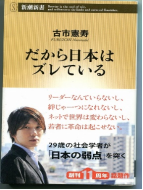 著者は1985年生まれというから、まず驚きました。不思議の国の「大人たち」と副題にあり、謎に包まれている「大人たち」を観察記録したものと、多々述べられています。いくつか気に留まったところのみ抜粋しました。
著者は1985年生まれというから、まず驚きました。不思議の国の「大人たち」と副題にあり、謎に包まれている「大人たち」を観察記録したものと、多々述べられています。いくつか気に留まったところのみ抜粋しました。
「強いリーダー」を待望するだけで、自分からは動き出さない。
「クール・ジャパン」や「おもてなし」と言いながら、内実は古臭い「挙国一致」の精神論。
実力主義の時代だと煽りながら、結局はひとを学歴や社歴でしか判断できない。自分ではITを使えないのに、やたら「ネット」や「ソーシャル」の力を信じている。
これらの「勘違い」はどこから来るのだろうか。国や企業の偉い人たちのこうした考え方は往々にして、ピントがズレていたり、大切な何かが欠けていたりする。
「リーダー」なんていらないの項では、
日本には強いリーダーや真のリーダーがいないと言われる。それは別に嘆くことではなくて、むしろ喜ぶべきことだろう。強いリーダーがいなくとも大丈夫なくらい、豊かで安定した社会を築き上げたことを誇ればいい。首相が毎年のように替わってきたことをもっと自慢しても良いくらいだ。日本は一国のトップが誰であろうとも、政治も経済も問題なく回っていくほど成熟した国家なんだと。
一番参考になった、情報発信という項に、
「誤解されない話し方、炎上しない答え方」(ディスカヴァー・トゥエンティワン)という本では「炎上しない話し方」として次のポイントが指摘されている。
ネガティブな話をしない
差別的な発言をしない
犯罪を肯定するようなことは言わない
批判は慎重に話し相手を錯覚しない
他人に関わるコメントは根拠と説明を十分に
特にツイッターでは人権意識などに対して感度が高い人が多数生息しているうえに、感度は高くないが勝ち馬には乗りたい迎合主義者が溢れている。ちょっとした発言が大炎上のもととなる。
私自身もいろいろな現状批判されている記事を読んでいると、言っていることは多分正しいのだろうが、気が滅入るというか、読むのが億劫になってくることがありました。おそらくこの六つのポイントに関連していると思い、自分自身、肝に銘じておきたいと思いました。
この書感もズレているかも知れません。
(ジョンレノ・ホツマ 2015年1月15日)
悲しい歴史の国の韓国人/宮脇淳子(徳間書店 本体1,000円)
ちかごろ流行りの“嫌中本”“嫌韓本”の類いには食傷気味で少々うんざりしないでもないところがある。しかし本書の著者はまっとうな学者らしいので、売らんかなの題名やオビの惹きつけ文句は挑発的だが、内容はまっとうな韓国歴史を踏まえて論を展開しているはずだと期待して読んでみた。しかし最初に読後感?をいえば、確かにまっとうな韓国史を踏まえた論考とみえるだけに、なおのこと舌鋒鋭い韓国批判が際立っていて、正直なところそうとうに“嫌悪韓”を催す内容である。
まず本書のオビには「ウソで塗り固めた歴史があるかぎり韓国人の反日は終わらない」「永遠にわかりあえない困った隣人の本当の歴史とは?」とある。
本論ではまず、朝鮮は朝鮮半島だけで歴史が成立したことは一度もないという。つまり、李氏朝鮮500年はシナ(現中国)の属国、その前の高麗はモンゴルの統治、その前の高句麗、百済、新羅の三国時代の高句麗は朝鮮民族というより北方騎馬民族であり、その上この国は王が代われば前者の遺蹟を抹殺してきたので歴史の継続性がないという。
また韓国人が日本を目の敵にするのは、日本人が韓国人をつくったからだという。つまり日本人が朝鮮半島に進出し、独立させなかったら、彼らに朝鮮人、コリアンだという民族の自覚も国家の意識も朝鮮史という歴史感覚もなく、シナ史の一部になっていただろうという。
李氏朝鮮の太祖、李成桂の祖先は「李朝太祖実録」では新羅の大臣だったというが、父はウルスブハという女真人であり、李成桂も女真人だと本書は指摘する。朝鮮史の歴史文献は「いいわけとウソとこじつけ」で、まっとうなことはひとつも書かれていないという。
李氏朝鮮は、両班(りょうはん=ヤンバン)、つまり文班(文官)と武班(武官)という一割の特権階級の下に5階層の身分制度があり、500年にわたってこの階級が固定化され、農業も商業もすべて横ばいで発展しなかった。それどころか高麗時代は飼育していた羊もいなくなり、技術もすたれて荷車も作れなくなり、染料がないので白服になったという。
類書がよく取り上げる「七奪」は、日本が韓国から取り上げたと韓国がいう「主権、国王、人命、国語、姓名、土地、資源」だ。実際は、「主権」では清国の属国だった李氏朝鮮に主権はなかった。「国王」では、李王家を日本は皇室の一員として厚く遇した。「人命」では日本の統治下で人口が増大し、「国語」では日本語を話せる韓国人は16%だったが強制せず、朝鮮語辞典まで作って両班が独占していた正しい朝鮮語やハングルの普及を図った。「氏名」では、それまで両班以外の韓国人は「姓」を持たなかったが、統治後29年も立ってから朝鮮人の要望で日本的な名前を自由に名乗る「創氏改名」を認めた。「土地」では朝鮮半島で日本人が所有していた土地はわずか6パーセントだった。「資源」では産業の育成、インフラ整備で韓国予算の25%、統治の35年間で現在価格63兆円を注ぎ込んだ。かくして日韓併合は朝鮮半島の日本化、近代化であって欧米列強のやった植民地化ではなかったと本書はいう。
近年においては、日本は先の戦争で朝鮮と戦争したわけではなく、彼らも日本人として戦ったはずだが、戦後彼らは戦勝国民のようにふるまった。李承晩は政敵を暗殺して初代大統領になり、選挙に反対する済州島民6万人を虐殺し、勝手に李承晩ラインを設定して排他的経済水域を拡大した。これが今日、韓国が竹島を実効支配する原因となっている。
こうして本書は困った隣人を容赦なく描く。事実を捻じ曲げた歴史認識を言えば言うほど、韓国は自己矛盾に陥るしかなくなるというのが「朝鮮通史」としてまとめあげた本書の主張である。そして著者は、自由な思考の材料になる歴史の真実だけを提供するのが学者の使命だという。とはいうものの、やはり“嫌悪韓”の色濃く漂う一書である。
(山勘 2015年1月15日)
前回、箱根の語源となった箱根神について述べさせていただきましたが、もう一つの重大な背景を忘れていることに気が付きました。
箱根神となられた「オシホミミ・オシホミ命」(天忍穂耳尊)は生まれながらにして、身体が弱く・・・と、あり、外へはあまり出ず、常に部屋の中に居られたから、その思いから自分は箱の中の根っことなって、二人の子供・皇子を下から支えているから、大きく育って羽ばたいてくれという願望だと考えていました。
しかし、生まれた背景、日嗣皇子になられた経緯を見直すと、底知れぬ陰湿な陰謀・恨みから、命を狙われている危険があったことに気が付いたからです。
ホツマツタヱ6綾から、天照神の子供は五男三女で、生まれた順番は
1.長男「ホヒノ命・タナヒト」(マス姫・モチコの子)
2.長女「タケコ・オキツシマ姫」(コマス姫・ハヤコの三つ子)
2.次女「タキコ・エツノシマ姫」(コマス姫・ハヤコの三つ子)
2.三女「タナコ・イチキシマ姫」(コマス姫・ハヤコの三つ子)
3.次男「オシホミ命・オシヒト」(サクナタリ・セオリツホノコの子)
4.三男「タダギネ・アマツヒコネ」(ハヤアキツアキコの子)
5.四男「バラギネ・イキツヒコネ」(オオミヤミチコの子)
6.五男「ヌカタダ・クマノクズヒ」(トヨ姫の子)
となり、本来は「マスヒメ・モチコ」が生んだ「アメノホヒ・タナヒト」が日嗣皇子であったわけです。
しかし、その後中宮に入られた「サクナダリ・セオリツ姫・ホノコ」(通称ムカツ姫)が、「オシホミ命・オシヒト」という男の子を生みます。天照神の2番目の皇子になります。この2番目に生まれた「オシホミ命」が今で言う皇位継承の皇子になったわけです。
「タナヒト」が皇位継承者として、皇子を生んだ母親も、母親の出身地の豪族たちも喜んでいたわけですが、突然、皇位継承を棚上げされてしまったわけです。この仕打ちに恨みを持つようになり、後に「おろち」と化(か)する発端がここにあったと思われます。
ホツマツタヱ12綾に「オシホミミ」のご成婚の記述があり、天児(あまがつ)といって、災難が降りかからないように身代わりになってくれる人形のことがでてきます。
以前、此処だけを単独で読んだ時には気が付かなかったのですが、妬みを持った何者かに命を狙われていた形跡があったからです。出かけるときは身代わりの人形を用意し、廻りをガードされていたことが窺えます。
この、命を狙っていた背景については記されていませんが、前後関係から自ずとわかり、「オシホミ命」本人から見れば自由度がなく常に箱の中に閉じ込められていた心境であったと思われます。
よって、この「オシホミ命」は常に箱の中で生活されてきたし、死後も箱の中に留まってという意味合いであったように理解いたしました。
本来であれば、自分が亡くなる前に、次の日嗣皇子を決めなければならなかったのに、どちらとも決めず、二人に仲良くやれと託したのは、自分のように狙われないように、危険分散して、自由に生きて欲しいという願いが強かったからだと思いました。
(2014年12月25日 ジョンレノ・ホツマ)
これは正月早々に見聞きした、たわいもない3つの話である。笑える話と、不愉快な話と、チョッピリ嬉しい話である。“仕事始め”もない年金暮らしの身としては、未だお屠蘇気分の尾を引く正月6日の、まずは笑える話である。
その日の午後2時ごろ、高尾方面に向かうJR中央線の新宿駅で、高齢のおじさん2人とおばさん1人の3人連れが乗ってきた。シルバーシートに座っていた私の横2席と向かい側の1席が空いていた。向かい側に品の良いおじさんが座り、こちらでは、ガラッパチ?のおじさんが、おばさんに「あんたオレより上だろう。歳の順だからお座りよ」と勧める。おじさん2人は小さなビニール袋を手に下げている。袋の四角ばった形状は、升酒の小さな升が入っているらしく見える。どこかで樽酒でもふるまわれてきたらしい。たしかに顔も少し赤みがあり微薫を帯びている。
いくつになったかと迫られたおばさんが、小声で「今年で9よ」。これを聞いておじさん、大きな声で、「ほー79か。じゃーオレが座るか」。チラと拝見すると、当惑気味のおばさんの顔はあまりしわもなく70前後にも見える。つり革につかまって立つおばさんの背に、向こうの“品おじさん”が「私は次の駅で降りるからね」と声をかける。
その後の“ガラおじさん”の話があきれる。人間足腰が大事だ。オレは下着を履くときもなるべく片足で立って履くようにしている。ただ、ズボン下の方はいいがパンツの時は足を高く上げなくちゃならないので危ない。タンスにでも寄りかかってやれば大丈夫だがね」といった調子の話が続く。
やっと次の駅が近づいて、「はい下りるからね」と“品おじさん”が早めに立っておばさんに席を譲った。おばさんが座った途端にその隣の客も下車して行った。おばさんの横にすばやく“ガラおじさん”が滑り込んで、「彼、今度来ると言っていたがホントかね」と話が続く。
次は不愉快な話。国分寺駅近くの路上で、ボランティアなのかいつも中高年の数人が制服制帽姿で交通整理をしている。交通整理といっても交差点での整理ではなく、近くの大学から駅に向かう、さほど広くもない歩道の真ん中に立って、行く人来る人、左右歩行者がごちゃ混ぜにならないように分離誘導しているのである。
6日の午後4時ごろ、路上を走ってきた一台のバイクが停まりかけ、歩道を横切ってガソリンスタンドに入る姿勢を見せた。それを見た、割りに若い中年の“制服制帽”が、「入るのかな」とつぶやき、「ちょっと待って」といって私の胸先に腕を出した。腕が私の胸に触れた。不愉快だったので制止を無視してそのまま進んだ。「腕が胸に触れるようないきなりの制止は失礼ではないか。『ちょっと待て』と制止する相手はバイクの方ではないか」と、考えた。
最後に良い話。6日の夕刻、小田急線のある駅で乗った車両のシルバーシート。向かいの3人席の端に、旅行帰りらしい大きなバックを前にした中年の女性客が1人。その隣の空席に飲み物の空きビンが転がっていた。こちらの私が座った横の席にはビールの空き缶が転がっていた。どうやら同じグループの“犯行”と思われる。向こうのご婦人はいっこうに空きビンに関心を示さないが、私の方は空き缶が気になってしかたがない。
次の駅で中年の男性が乗ってきた。この男性も大きな黒いバックを持っていたが、席に座った途端に、なんの躊躇もなく空きビンを取ってバックの横ポケットに押し込んだ。次の駅で私が下車した。真似をしたようで気恥ずかしかったが勇を鼓して空き缶を持って降りた。
ホームで背の高い若い駅員さんが発車のアナウンスをしていたので、終ったところで「これ、座席にあったゴミだけど」と渡したら、「あ、ありがとうございます」と明朗な声でお礼をいわれ、きわめて自然に受け取ってもらった。ちょっぴり心が温まった。
(山勘 2015年1月15日)
こんなことがあっていいものだろうか。新年早々、世界の耳目を驚かしたのは、イスラム教の預言者ムハンマドの風刺画を掲載したフランスの政治週刊紙襲撃事件だ。編集長ら12人が殺害された。ことの発端は命の重さと釣り合わぬ風刺画、漫画である。
過去において、ムハンマド風刺漫画の掲載でイスラム諸国との外交問題に発展したケースは2005年のデンマーク日刊紙にはじまり、その後欧州諸国で何度か繰り返されてきたようだが、ついに今回の惨劇を招いてしまった。これを風刺画、漫画の力とみるか、たかが漫画でブチ切れるイスラムの凶暴化とみるか。そも風刺画とは何か、と考えてしまった。
今回の事件では、自由諸国の首脳をはじめ多くの自由市民が参加して抗議のデモが行なわれた。欧州首脳が腕を組んでデモの最前列に立つニュースに驚いて、オバマ大統領など首脳クラスをデモに参加させなかった米国では内省と批判の声が挙がったという。
こうした世界の動きに力を得て、仏紙は、再びムハンマド風刺画を表紙にした特別号を500万部発行した。この特別号を買い求める巷の様子がテレビニュースになり、私などは野次馬根性もあってその表紙を見たいと思ったがなかなか映してくれなかった。新聞も産経など何紙かはその風刺画を掲載したようだが大手の讀賣、朝日、毎日は掲載しなかった。掲載しなかった理由は、イスラム人口の大きいことに配慮して、イスラム教を冒涜したりイスラム教徒を侮蔑する恐れがあることに配慮したらしい。しかし、こうした、イスラムの“反動”を見越したマスコミの自己規制も、表現の自由を考える上で大きな論点となろう。
本題の風刺画だが、「日本語大辞典」によれば、「風刺画」とは、「社会または個人の過失・欠陥・不合理・罪悪などを批判、非難した絵画。とくに風刺性や寓意性・暴露性の強いものをいう」とあり、「漫画の一分野としては政治漫画、思想漫画のジャンルを形成する」とある。この説明の中のキーワードは「批判」だが、同辞典によれば、「批判」とは事柄の「正しさ・よしあし」などを「批評」し「判断」すること、である。
さらに、風刺画の寄って立つべき原義の「風刺」については、「社会や人物の欠陥をユーモアに包んで批判すること。古くは落首、川柳、狂歌などにみられ、近代の文学、漫画、芸能などの重要な表現手段」とある。ここでは「ユーモア」がポイントである。
したがって日本の落首(落書き)、川柳、狂歌の神髄はユーモアのある諧謔性にあり、ストレートパンチの強烈な攻撃性を持たない。かたやフランスのユーモアにはフランス小話といわれる“下ネタ”などの軽快なユーモアがある一方で、政治や社会風刺では強烈に攻撃的な面があるといわれる。ムハンマド揶揄にはそんなストレート・パワーがあるのかもしれない。
ともあれ、ムハンマドに対する批判、「正しさ・よしあし」の批評と判断は自由主義諸国とイスラム圏では真っ向から対立する。イスラム教徒にとっては「命がけの宗教」を、不用意に?風刺して「表現の自由」を振りかざすのはどんなものか。
事件の翌週、アジア歴訪中のローマ法王フランシスコ(78)が、「言論の自由にも限度がある」と述べ、発言の本旨から少し脱線して「もし自分の母親がののしられたらパンチをお見舞いするだろう」とパンチの身ぶりを入れて語ったと報じられる。風刺のユーモアがある。もちろんそれはテロを容認するものではなく「神の名による殺りくを強く非難」した上で(イスラム教も含めて)「他の人の宗教を侮辱してはならない」と述べたもので、その言は重い。
基本的にいって「悪意」「脅迫」「陰湿」「侮蔑」「冒涜」など陰性な攻撃性は風刺の精神、風刺画の本道ではないのではないか。やはりムハンマド戯画化は行き過ぎで表現の自由にも限度があると言うべきだろう。ただしテロと表現の自由とはローマ法王の教えを待つまでもなく別である。テロは断固封じ込めてもらわなければならない。
(山勘 2015年1月19日)