2018年11月22日(木)午後3時~午後5時(会場:三鷹SOHOパイロットオフィス会議室、参加者:狸吉、致智望、山勘、恵比寿っさん、ジョンレノ・ホツマ、本屋学問)
所用が続いて参加いただけなかった致智望さんが2か月ぶりに参加で、久しぶりに全員集合の活気ある会になりました。会前の雑談で日産のゴーン氏のことが話題になりましたが、最近の日本企業には外国人役員が増え、給与も日本人を上回っているそうで、何か明治時代のお雇い外国人を思い出しました。今の日本企業のトップにはビジョンも投資意欲もない、つまり何をして良いかわからないとか。政府の国防、経済、労働、健康保険、移民といった対策がすべて場当たり的なのは、政治家始め国全体が劣化してしまったからだという厳しい意見も出ました。本会はそうならないよう、さらに切磋琢磨を続けましょう。
(今月の書感)
「日本人の知らないトランプのアメリカ」(致智望)/「樹と人に無駄な年輪はなかった」(ジョンレノ・ホツマ)/「体力の正体は筋肉」(恵比寿っさん)/「立ち上がれ日本人」(本屋学問)/「感性は感動しない 美術の見方、批評の作法」(山勘)/「平成論―「生きづらさ」の30年を考える」(狸吉)
(今月のネットエッセイ)
「またも出ましたデータ改ざん」(山勘)/「「人間」抜きの?「移入労働力」」(山勘)
 著者の日高義樹は、1959年NHKに入局し、ワシントン特派員をかわきりに、ニューヨーク支局長などを歴任し1992年退職後、ハドソン研究所首席研究員として日米関係の将来に関する調査、研究の責任者を務める。NHK特派員として、カーター大統領への取材がはじめて、それをきっかけに、ホワイトハウスのスタッフと繋がりが出来て、以来取材ができるようになったと言う。当時の米国には、敗戦国の日本には特殊な感情が有って、カーター大統領も例外では無く極めて幸運な時期に恵まれたと言う。
著者の日高義樹は、1959年NHKに入局し、ワシントン特派員をかわきりに、ニューヨーク支局長などを歴任し1992年退職後、ハドソン研究所首席研究員として日米関係の将来に関する調査、研究の責任者を務める。NHK特派員として、カーター大統領への取材がはじめて、それをきっかけに、ホワイトハウスのスタッフと繋がりが出来て、以来取材ができるようになったと言う。当時の米国には、敗戦国の日本には特殊な感情が有って、カーター大統領も例外では無く極めて幸運な時期に恵まれたと言う。永い間の取材経験から45代大統領のトランプをみると、トランプは政治の素人であり、ビジネスの感覚でアメリカの政治を動かしているから、その周辺は変化の大きさに幻惑され、マスメディアや政治評論家たちは変化の実像を捉えきれないでいる。そのことに、トランプがハラをたて「フェイクニュース」とよぶ報道に繋がっていると言う。
トランプのアメリカは、想像を超えた大変化を起こしつつあり、その変化の実像を日本人に伝えたいというのが本書の上梓となった。
経済の伸びが、オバマ時代の2倍になった。それは、トランプの減税策が大きく貢献している。その政策の特徴は、企業の投資に対し、その全額を納税額から控除すると言う減税政策で、投資資金がそっくり経費扱いとなり、その結果モルガンスタンレーなどは、資金の投資という行動が出来なくなり、ウォール街での活動を殆ど停止せざるを得なくなったと言う。(致知望意見 : 投資減税策は、企業経営に極めて有効であり、特に起業の初期には絶対に必要な策であり、ビジネスマンの起業意欲が向上する事間違いが、過去に行われた例は記憶にない)
トランプの歴史的減税によって、大きな景気の到来を期待して、低迷していたトランプの人気がようやく上がり始め、大統領弾劾の話まであったが、支持率50%を超す結果が出ていて、この政策は我々中小企業にとっては「そうあるべき」と考える当然の善政である。
一方の国家安全保障戦略については、「極東の範囲」という考え方が無くなっている。安倍政権は、中国の侵略から尖閣列島を守るために日米安保条約を頼りにしているが、このストラテジーからは、日米安保には言及されておらず、さらに、西太平洋、極東と言う考え方すらも消えてしまっている。
アジアの安全を考える基本的な地勢範囲としてアメリカ西海岸からインド洋、アフリカ大陸の東海岸までをひとまとめにしている。日本を防衛するための極東の範囲と言った考えは、アメリカの戦略構想の中から締め出されたと言う。
トランプが1年の間に、たて続けに新しい国家戦略を構築したのは、ロシアや中国と比べてアメリカが決定的に強力であると言う実態を失ってしまったからで、それは、クリントンを含めて、24年間の失策がトランプ政権にのし掛かっているからとトランプは言う。
トランプの強硬な貿易政策は、「貿易戦争の始まり」と言うけれど、トランプの政策は不法な経済活動によって、経済が拡大した中国の政治権力をより強化する習近平に対する戦いの宣言と言う。
習近平は、軍事力を使わずに、経済の拡大によって主席任期の地位撤廃という中国皇帝の地位を得たこととなり、ナポレオンにも出来なかったことを成し遂げてしまった。
しかし、その実態は水増しされた経済拡大と、それを背景にした権力闘争の勝利等の実績しかないとみている。
トランプ叩きは、大統領にたいする反乱謀反にもみえるほど激しく常識を逸している、健全な政治システムが、アメリカと言う国の根本を揺るがす大きな変動が始まっているように思える。これは、クリントンが大統領になると思っていた人たちの政治体制に関わる官僚、リベラル派の政治家、そしてマスコミの人たちにとって、大番狂わせの結果であり、アメリカの歴史を否定するものと、著者は大きな問題として提起している。
トランプが、充分な準備をしないままに、アメリカの複雑な政治体制の中に踏み込んでしまったことで、アメリカが大きな危機を迎えてしまったことに著者は憂いでいる。そして、トランプの政治的危機は、これからもさらに深刻なものになる。それは、アメリカの現在の政治的混乱と危機的状況は、トランプの用心に欠けた行動の自業自得であり、その先には第三期政権を抱いたオバマの反逆が、大きな原因となることは間違いと言う。
トランプの経済政策について言うと、オバマの規制と社会主義的な政策を撤廃することにより、アメリカ経済を急速に立ち直らせた。税金を払っていない人々のために、政府が多額の援助を行うと言うオバマの福祉偏重政策を税金の無駄使いと言い切る。企業向けの減税はいくら増やしても構わない、それにつれて経済が拡大し国の収入も増える。今のままでは、向こう10年はアメリカの収支バランスが改善するとは考えられない。強気で押しまくるのが、トランプ流でこのギャンブル的政策による財政赤字とインフレを長い目でみた経済拡大の要因として、抱えて行こうとしている。それで、現状のアメリカ経済はインフレが視野に入り好調を続けると言う。しかし、経済拡大にも関わらず財政赤字は減らないことが明らかになっていて、世界の投資家がドルに魅力を感じなくなっている。その原因は3つあり、一つは経済拡大によって、賃金が上がっている。2番目は、製造業が伸びていない。3番目は、貿易赤字が拡大している。要は、甘やかされた労動者と積もり積もった財政赤字が、急に動き出した経済活動にひずみを生じさせたと言う。
大統領のドクトリンを考えてみると、大統領が基本原則を持ち、大統領としての矜持、そして大統領としての業績を纏めたもの。それを以て、アメリカの「力」に対する信頼によって世界を動かすと言うドクトリンに欠けるのがトランプであり、加えてアカデミックな世界とのかかわりを初めから絶ってしまっている。専門家たちは、トランプがいつかアメリカを危機に追い込むのではないかと強い懸念を抱いていると言う。
ホワイトハウスを良く知る著者が日本の有るべき姿を暗示する見解を最後に述べている。トランプの政策は、対中国、対ロシアについて過去の大統領達のミスジャッジを補うべく、真っ当な政策を取っていると著者は言う。
アメリカ政治の奥の院たるホワイトハウスは、魑魅魍魎で一筋ならではの状況であり、トランプはこの状況のホワイトハウスには寄り付かず、ドランプタワーで生活し、自分の別荘で海外の賓客を接待している。ホワイトハウスは、アメリカの軍事拠点であり、指揮機能が集中した場所である。過去の大統領も良きにしろ、悪きにしろ、この組織をフルに活用してきた。その弊害は、無責任な政治を進めたケネディ、アメリカを社会主義体制にしたオバマのように、大きな組織の責任者を務めたことのない、軽薄なイデオロギーの政治家が、マスメディアに動かされ簡単に多数派に組み込まれてしまう仕組みもある。トランプは、この仕組みになじまず、行動していることが危険と言う。
アメリカのあるべき姿を愚直に実行しようとするトランプの行動は、アメリカの歴史が構築してきた仕組みに対し、自分に合わない仕組みとして挑戦している。トランプは、アメリカ経済を立て直し、アメリカの時代を続ける姿勢を明確にしている。しかし、重要なことは、アメリカを動かしているホワイトハウスを自らの見識と器量で機能するようにしてからアメリカの敵と戦わなければならない。トランプが問われているのは、まさにこの一点と著者は言い切る。
日高義樹の本書は、アメリカの恐ろしい現状をレポートしていると見た。今のアメリカには、アイゼンハワーのような優れたリーターを必要としていることも、著者は暗示している。
(致智望 2018年8月30日)
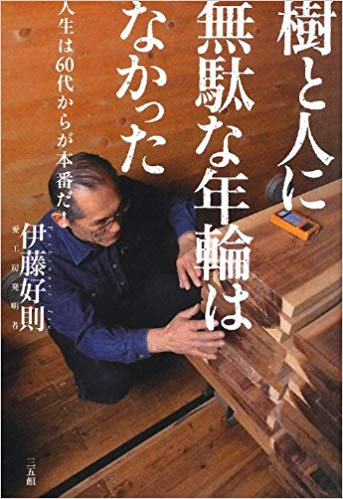
著者は1941年生まれ、「愛工房」という木材乾燥装置を作り上げた。木の立場に立って、木を生き物として捉え、木が気持ちよく汗を流してもらうように45℃という最適の温度を見つけ45℃の木材乾燥装置を完成させた方です。
森林の再生により、林業の活性化と安全な住まいの必要性を説いており、そのキーワードが杉の活用であることを説いています。
現在、木や地球が疲弊し始めていることに対し、木が出している酸素や水を素直にありがたいと思う気持ちが著者の根底にあり、大事な木の成分・酵素が生きていられる温度が45℃であることを、実験を通して確認し、この乾燥装置を完成させた。乾燥装置の建物全体が湿度を逃がす透湿性のあるものを使い、そのためコンクリートや金属は使わない。
杉は、場所により白目・赤目(黒心)と呼ばれ、特に黒心は10年かけて乾燥するとどんな木より強く、腐らず、カビず、虫に食われない。杉は日本の隠れた財産であり、神木とも言われている。
杉には私たちを癒す力がある。杉の学名はクリプトメリアジャポニカ(日本の隠れた財産)というように、まさに日本の隠れた財産です。
森林浴など、木には癒しのイメージがあり、癒し効果も実証されている。ヒノキの芳香には覚醒作用があり、杉には鎮静作用、ヒバはその中間であることがわかっている。
しかし、現状では、杉は乾燥しにくいと嫌われ、大量の外材消費に繋がってしまっている。今までの木材乾燥機は高温で処理、重油ボイラーで加熱した高温蒸気を送り乾燥させている。
木は木材になっても生きて呼吸しているが、高温乾燥機を経た結果、ただの木材になってしまい、木が本来保有している病虫害と闘う成分や免疫力を失っており、建材として使われたとき、シロアリなどの襲撃に無力で終わる。そこで薬剤を使う。人間の体と同じで、免疫力を失わせておいて薬を使う。利益を上げるのは製薬メーカーと取り扱う業者だけです。
日本住宅新聞(2004年8月)によると、日本は世界人口の2%なのに、世界で流通する木材の34%も消費し、その国内消費の82%が外材で、国産材は18%。国土の67%が森林で、森林面積は2500万ヘクタールあり、森林率でみると、フィンランド、スエーデンに次いで世界3位の森林大国なのです。そして毎年、世界人口2%の日本が世界中で木材の約1/3を消費しており、木材の大量消費大国でもある。
その弊害が例えば2006年フィリッピンで大規模地滑りが発生し、山をのみ込んだ黒い土砂は小学校を押しつぶし、3500人が住む村が消えたと報じられ、30年ほど前から森林が広い範囲で伐採されていたそうです。専門家は降雨時の土砂災害の危険性をしていたが、政治家と業者の利権が絡んで違法伐採が横行していた。そのほとんどが日本に来ていると思われる。
生命を奪われた身内の人たちは、日本への恨みを忘れることはないでしょう。これからもこのような災害が起こらない保証はありません。地球環境破壊の元凶が日本だったと非難される日が来ないことを祈るばかりです。
将来的な日本バッシングも心配している。輸入する木材資源が日本になければまだしも、木は日本中に有り余っています。今後、木材は地球資源として価値が高まると考えられるとき、今まで日本は自国の木を温存して外国から奪ってきたという批判が起こりうる。バッシングの矢面に立つのは私たちではなく、次世代の子供たちです。
今、農業の世界では食料自給率の低さが問題になっているが、せめて衣食住は自給自足を目指すべきではないでしょうか。せめて外材比率を30%以下に引き下げる必要があると考えています。
一般的な木造住宅に於ける木材の総額は建築費の10%にも満たない。著者の言う本物の木造建築物では木材費用が20~25%。本物の(呼吸する・生きている)木材が多く使われ、化学建材や無駄な高級商品が制御され一石二鳥。本物の木を使うことで住まいが生命を守る住宅になる。
生命を考えたとき、先に棲息した木は自らが生きるための環境づくりをし、その周囲に棲む生き物が育つための水や酸素を供給する。樹木の生存可能年数は1000年単位、動物はずっと短く死んで、土中の養分となり木の生存に役立ってきた。日本の木はその種によって棲むべき場所に棲み他の生き物たちと共生してきた。第2次世界大戦前の100年前、日本人のライフスタイルは、地球の命、人の命、木の命にとって、一番いいことをやっていたと思う。石油化学製品や化学的な添加物などはなかった。
生命を守る住まいとは、呼吸する素材を使用している住まい。
現在のハウスメーカーは石油を原料とした化学建材には化学物質を放出するものが多い。人体の健康を損なうだけでなく、脳に対する影響も懸念される。昔は考えられなかった犯罪が多いことや、近年の肉体的、精神的な障害の原因が住まいにある可能性が高い。
どれだけ儲かるものをつくったとしても、それが環境を壊すものや生命を脅かすもの、そして将来的に負の遺産になるものであっては、絶対にいけません。子孫に何を残すのかが問われている時代です。
国策の下で、私たちの年代は生まれてまもなく戦争の犠牲になりました。そして今また、「原子力は国策」としてすすめてきたリスクを味わうことになっています。本来、国策とは国民のための対策であるべきはずなのに、国民を犠牲にする対策となっています。
モノづくりの現場にいる方には、生命を優先すれば、自分にも周りにもいいことが起こるとわかっていただきたいのです。たとえば、農薬を使用しないことで一番得するのはその農家です。毒にまみれた野菜や果実を扱うことで、扱っている人の命も蝕まれていることに気づくべきだと思うのです。農薬を使わないで損するのは薬品メーカー、機械、そして巨大な天下り先だけ。消費者の意識が変わっていきつつあるのですから、選ばれる仕事内容であるべきです。
また私は、人間以外の命でも簡単に奪うことにも反対です。農薬で殺す虫も、植物にとって本当に害なのでしょうか。虫が死んだら土に還って養分になるので、そのおかげで植物は生きていける。それなのに、人間サマの実利を脅かすからと殺虫剤を撒く。こんな愚かなことはありません。
単純に人間の目線で害と益を判断しているだけ。自然の命の目線では見ていません。人間は自分たちだけで生きていけると思ったら大間違いです。地球の命、木を含めた他の生き物たちの命があって私たち人間も生きていけることを忘れないでください。
人間の命は樹木に比べたら短いが、選ばれた命を大樹のように太く逞しく生きようと結んでいます。
(ジョンレノ・ホツマ 2018年11月16日)
(ジョンレノ・ホツマ 2018年11月16日)

1949年愛知県生まれ。早稲田大学スポーツ科学学術院教授。教育学博士(東京大学)。
早稲田大学アクティブ・エイジング研究所所長。1971年名古屋大学理学部化学科卒業。1975年東京大学大学院教育学研究科修士課程修了。専攻は、健康増進に関する運動整理・生化学、スポーツ栄養学。ハンガリー体育大学名誉博士。
第20回秩父宮記念スポーツ医・科学賞功労賞を受賞。編著書に『からだの発達と加齢の科学』『ローイングの健康スポーツ科学』など多数。
はじめに
誰も避けられない体力の衰え
体の動くところに筋肉あり
筋肉は使わないとすぐに衰える“怠け者”
トレーニングは裏切らない
下半身と体幹の筋肉を鍛えなさい
筋肉にとっていい食事とはなにか
おわりに
参考文献
近年はwith aging(老いを)自然の流れとして、良いことは「年の功」として受け入れ、不自由なことがあったら知恵を絞って解決し、その人らしさを保ちながら、老いと上手に付き合ってゆく、という考え方)に加え、active agingという概念が加わっている。
アンチ・エイジングが「抗・老化」なら、ウィズ・エイジングは「共・老化」、アクティブ・エイジングは「脱・老化」といえよう。
全身に400種類以上ある骨格筋(これが体を動かす)は成人男性で体重の40~45%(女性で30~35%)だが、そのピークは意外に早く訪れ、男性は20~30歳(女性は20歳)ころで40歳くらいまではそのピークが何とかキープされる。その後は低下の一途。20~50歳の間に≒10%減少、50~80歳の間には更に30~50%と急激に減少する。
筋力・筋量の低下が著しいのは、上半身よりも下半身。歩かなかったり運動をしないと、ふくらはぎにある下腿三頭筋の減少率が特に大きい。目には見えないが、体幹筋(*1)も例外ではない。
体力は筋力と全身持久力。この2つを高めておけば、生活習慣病のリスクも減る。
日本人は世界一の座り過ぎ(シドニー大学の研究)。座っている間は下半身の筋肉は使われないので、全身の血行が悪くなる。座って30分で血流速度は70%も落ちる。しかし、80歳になっても90歳でも運動する習慣を身に付け、トレーニングを続けていけば、筋量は増加し、筋力は回復する。「もう遅い」はない、と著者はいう。
筋肉は使わないと低下するが、トレーニングをすれば増える。しかし、可逆性があるので、止めると元に戻ってしまう。また、効果が表れるのは2~3か月後である。自分の体力に合わせた負荷を徐々に増やすのが効果的なやり方。
特に大切なのは、下半身と体幹。
著者が勧めるのが「ローイング」(ボート漕ぎ)で簡単なチューブを使ってそれを引っぱるのが最も効果があるという。
*1:体幹筋とは①お腹周りの腹筋、横隔膜②背中周りの多裂筋、脊柱起立筋、広背筋、僧帽筋③腰回りの腸腰筋(大腰筋、腸骨筋、小腰筋)④おしりまわりの大殿筋、骨盤底筋を言うそうです。
(恵比寿っさん 2018年11月16日)
というわけで、買っちゃいました。 DEEDROフィットネスチューニングチューブセット(12ピース)。
¥2,099(税込み、Amazon)、いろいろな種類があって迷いますが、かなり安めのものを選択しました。
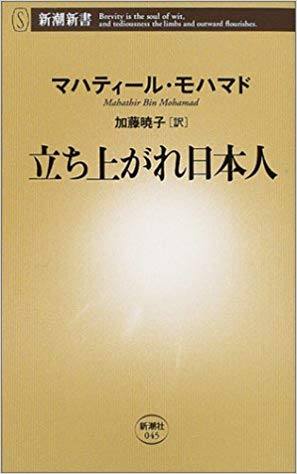
マハティールは、1981年から2003年まで22年間マレーシア首相を務め、2018年に15年ぶりに首相に返り咲いた。彼は1925年生まれなので今年93歳、この年齢で選挙を経て国家の指導者になった者はまずいないだろう。本書は、来日50回以上という親日家で知られ、日本を手本にした「ルック・イースト」政策でマレーシアの近代化を推進した、アジアが生んだ偉大な政治家マハティールの日本観を始め、独自の政治論や外交政策論をまとめたものである。
訳者は毎日新聞社時代にマハティールの知遇を得、その後も来日時の案内役を務めるなど個人的にも親交があり、巻末に「アジアの哲人宰相」という解説も書いているが、彼の人物を知るにはむしろこちらから読み始めたほうが理解しやすいかもしれない。
イギリス統治下のマレー半島北部、インド系イスラム教徒で英語学校校長だった父と、厳格な家庭に育ったマレー人の母との間に生まれたマハティールは、イギリスの植民地政策に不満を抱きながらも法律家を夢見てイギリス留学を目指すが果たせず、戦後は現在のマラヤ大学で医学を学んでマレー人として初の開業医となる一方、学生時代から積極的に行なっていた政治活動を本格化した。
日本占領下でマハティールは、学費を稼ぐためにコーヒーやピーナツを売っていたが、「イギリス人は金も払わず商品を奪うことさえあったが、日本の軍人は端数まできちんと払ってくれた。日本人は皆折り目正しく、勇敢で愛国的だった」と振り返る。このようにイギリス植民地時代の経験が欧米批判の動機になり、皮肉にも日本占領下での体験が逆に日本人への好感情になっている。
日本は敗戦後、軍国主義が非生産的であることを反省して、全エネルギーを国民が安全で快適に暮らせる平和国家の建設に注いだ。製品の品質を下げずに生産コストを削減し、贅沢品だったものを誰でも入手できる、まさに奇跡ともいえる成果をつくり上げた。
1961年に初めて日本を訪れたマハティールは、水田の真ん中に建つ松下電器の工場に、日本橋の上に建設中の高速道路に驚き、人々が国家再建と経済発展に献身的に働く光景を目の当たりにして、日本と日本人のダイナミズムを体感する。そして、訪日のたびに変貌する日本と、高い規律と職業倫理観を持って高品質な製品をつくり上げる日本人の姿勢に心を打たれ、マレーシアは日本に学ぼうと考えたとマハティールは書いている。
彼は、日本が成功した要因を「愛国心」、「規律正しさ」、「勤勉さ」、「能力管理システム」ととらえ、政府と企業と国民が密接に連携して社会と産業を効率良く発展させる「日本型システム」を導入する。その結果、人口2300万人のマレーシアは他の発展途上国に先駆けて世界18位の貿易国に成長した。東アジア全体としては、1960年のGDPがヨーロッパの42%、アメリカの23%だったが、1990年にはヨーロッパの67%、アメリカの73%までになったという。
欧米はアジアに干渉して自らの主張を押し付け、その経済発展を妨げてきた。アジア・アフリカなど貧しい国から輸出する原材料の価格は、買い手が欧米しかないため最低水準で、市場における開発途上国の立場は弱まり、輸出品の価格を引き上げる代わりに融資と援助が与えられる。
一方、IMF(世界通貨基金)も欧米寄りで、経済危機のときにマレーシアはその処方箋を受け入れなかったが、もし彼らのいうとおりにしていたら国家は崩壊していた。先進国は自国の利益だけを追及し、最終的にはIMFも通貨危機後の金融引締め政策が間違っていたことを認めたが、マレーシアが危機に陥ったとき、日本は味方になってくれたそうだ。
アジアで唯一新しい行政システムを導入して工業や経済の近代化に成功し、欧米の覇権主義と対等に渡り合った日本が、戦後は欧米の方向ばかり仰ぎ見ていたとき、東アジアは日本に熱い視線を注いでいた。長く欧米の支配下にあった東アジアは、日本が軍事進出したことで欧米も敗北することを知ったが、同時に東アジアの独立に大きな希望を与え、立派にやっていけることを証明したのは日本である。そして東アジア各国も日本に倣い、驚くような成長を遂げたとも書いている。
もし日本がなければ、欧米が世界の工業を支配し、彼らが基準と価格を決め、欧米しかつくれない製品を買うために世界は高価格を押し付けられていただろう。日本がなければ、東アジアの経済開発も強力な工業国家の誕生もあり得なかった。多国籍企業が安い労働力を求めて発展途上国に投資したのは、日本と競争せざるを得なくなったからで、日本と日本のサクセスストーリーがなければ、東アジア各国は模範にするべきものがなかった。
このように、東アジアが尊敬の眼差しで見ていた日本が、現在は国防、貿易その他ほとんどがアメリカの影響下にあるといっても過言ではない状況になっている。失業者を増やし、企業と社会の生産性を損なう外国のシステムを、日本はなぜ安易に受け入れるのか。アジアは欧米ではない。日本は終身雇用など独自の労働文化にもっと誇りを持つべきで、再び軍事大国にならないという近隣諸国の不安を取り除く保証さえあれば、もはや謝罪は必要ないとまで述べている。
中国を制御しながら東アジアをまとめられるのは、欧米ではなく東アジアの一員でもある日本以外にない。日本の低迷は、東アジアだけでなく世界にとっても大きな損失だ。今こそ立ち上がれ日本といいたい。マハティールは最後にこう結んでいる。
さらに、リーダーの条件として人の話を聞く耳を持つことで、その点で故小渕恵三首相を評価しているそうだ。アジアの人々は日本と日本人を尊敬し、友人でありリーダーであってほしいと期待しているが、現在のところ日本はそれに応えていないとも書いている。今の日本にマハティールのような政治家の出現を望むのは、?百年河清を俟つ”ようなものかもしれない。
(本屋学問 2018年11月19日)
感性は感動しない 美術の見方、批評の作法/椹木野衣(世界思想社 本体1,700円)

筆者椹木野衣(さわらぎやい)は多摩美術大学教授。読売新聞、朝日新聞の書評委員なども務め、「反アート入門」他、多くの著書を持つ美術評論家。
「はじめに」あるエピソードが面白い。著者の文章は、全国の国公私立大学の入試問題に使われているというが、そのうちの1つをある編集者が持ってきて解かせられたという。正解はなんと半分だったという。美術や美術評論文の解釈の多様性を示す話だろう。
それにしてもまずはタイトルの「感性は感動しない」というのはどういうことか。感動するのが感性ではないのか。いい絵を見て感動する。それが感性ではないのか。
その疑問に答えるために、筆者はまず岡本太郎の言葉を引く。
『感性をみがくという言葉はおかしいと思うんだ。
感性というのは、だれにでも、瞬間に起こるものだ。
感性だけ鋭くして、磨きたいと思ってもだめだね。
自分自身をいろいろな条件にぶつけることによって、
初めて自分全体の中に燃え上がり、
広がるものが感性だよ』
この岡本の言葉を、筆者は「至極まっとうな言葉だ」と肯定する。感性には実体がないのであり、どんな道具を使ってもみがけるはずがない、と言う。
そのうえで、芸術に必要なのは感性だと筆者は言う。そして学問やスポーツなど他の部門で必要とされる修行や努力は、芸術においては(かならずしも)必要ではないと言う。「見る人の気持ちがわけもわからずグラグラと揺り動かされる」、それが「藝術が作品として成り立つ根源的な条件」だと言う。
美大で教える筆者が、美術史や美学を教えてもそれによって美術家が良い作品を作れるわけではないと言う。見る側にとっても、知識や技術は鑑賞の助けにはなっても、それが邪魔になって目の前の絵や作品に感性が届かないことにもなると言う。
先の岡本太郎の言葉のなかの「いろいろな条件にぶつける」ことについて、筆者は、「誰でも、自分の心の中身を知るのは恐い。だから普段はそっと仕舞っておく。けれども、時に藝術作品はこの蓋を容赦なく開けてしまう」ことだと言う。作品から「ゴツゴツした感触」や「ナマの手触り」を感じるとき、私たちは、自分のなかで感性が音を立てて蠢いているのを初めて知る。感性とは、どこまでも事後的にしかしれないものだ、と言う。
以上は、本章に入る前の「感性は感動しない」から拾った話である。本章は3章からなり、「1 絵の見方、味わい方」では、絵を前に思いを巡らせること、簡単に感想は言わないことなど、鑑賞術を述べる。「Ⅱ 本の読み方、批評の書き方」では、書くための読書術、パソコンも使うが手書きを大事にし、息を止めて推敲する著者の流儀などを披歴する。「Ⅲ
批評の根となる記憶と生活」では、子供時代の記憶、音楽から批評家への道などを語る。
要するに本書は、絵の見方、評価の仕方、その作法を、著者の体験を通して実に平易で優しい語り口で述べている。
(山勘 2018年11月20日)

冒頭に大正大学の渡邊直樹文学部教授から本書出版の経緯についての説明がある。教授は平成の世は宗教絡みの事件やニュースが多いことに気付き、東京工業大学リベラルアーツ研究教育院の教授4人(本書の著者)に働きかけ、2017年に「現代の社会と宗教1995~2017」と題する公開シンポジウムを開催した。シンポジウムの前後に講師4人による座談会を3回開催し、その議事録を加筆修正して本書は出来上がったとのこと。
出版の経緯からして本書の内容が宗教色の強いものであろうと予想したが、読んでみると宗教の解説でもなく宣伝でもない。「平成」という時代を読み解く鍵として宗教に触れているのだ。
池上彰による第1章「世界の中の平成日本」では、まず「平成とは何であったか」と、平成時代について総論を述べている。平成はバブル崩壊、オウム真理教によるサリン事件、9・11同時多発テロ、リーマン・ショック、東日本大震災など「激動の時代」であった。世界的には東西冷戦が終わり、政治の重しがとれて異なる宗教間の争いが激化した。世の中には漠然とした不安が広がり、「生きづらさ」を感じた日本の若者は、拠り所を求めてオウム真理教に入信する。キリスト教社会で不当に扱われていると感じたイスラム教徒は、過激派テロを起こしISに参加する。世界の多くの若者が「生きづらさ」を感じていた。彼等に救いを与えるのは宗教者の務めではないかと池上彰は問いかけている。
第2章「スピリチュアルからスピリチュアリティへ」で、弓山達也は日本での宗教を従来の教団宗教、何らかの精神性を持ったカルチャー、災害時などの「心のケア」を扱う活動の三つに分けると理解し易いと説く。この章では若者が何故オウムに惹かれたか、スピリチュアルとは何か、スピリチュアリティとは何かなど例を挙げて解説している。
第3章「仏教は日本を救えるか」で上田紀行は、高度成長の果てのバブル景気に酔い痴れ自信満々だった日本国民が、バブル崩壊、オウム真理教事件、福島の原発事故など、いわば「日本社会の底が抜けた」体験をし自信喪失に陥った。上田はこれを太平洋戦争の敗戦に次ぐ「第二の敗戦」と呼ぶ。この章で上田は旧態依然たる教団を叱咤し、新しい道を模索する若い宗教者たちにエールを送っている。
中島岳志は第4章「平成ネオ・ナショナリズムを超えて」で、平成を理解するキーワードとして、宗教の再活性化と政治の右傾化があると言う。宗教の再活性化は既存教団の活性化ではなく、60年代のヒッピーのように、新しい精神運動の活性化である。「生きづらさ」を抱えた若者たちにとって、ネト右翼やナショナリズムは魅力的な解決策に見える。ここに平成の危うさがある。
最終章の「おわりに」で上田は、「平成とはいったいどんな時代だったのか?」と問いかけ、「そう聞かれてすぐにきちんした返答ができる人はいない」と続けている。「昭和の時代」は「戦争と敗戦、戦後の経済復興と高度成長」と時代区分がはっきりしている。
しかし、「平成の時代」は世界中でいろいろなことが起こり、時代を描写する言葉を見つけるのが難しい」と言い、さらに、「この本は、その『平成論』に宗教の視点から斬り込もうとするものです」と本書刊行の狙いを明らかにしている。
小さな文庫本だが内容はずっしりと重かった。
(狸吉 2018年11月21日)
企業のデータ改ざん事件が続く。企業不祥事の原因は、一言で言えば「人間」である。どこからわが国製造業の人間的な“ゆるみ”が始まったのだろう。今回、製品検査データの改ざんが露呈したKYB㈱は、3年前に社名変更。それ以前は、戦前からの社歴を持つ優良企業の「カヤバ工業」だった。
同社の、免震・制振ダンパーの検査データ改ざんは2003年ごろから続いていたと言われる。同じような事件は2015年に発覚した東洋ゴム工業の免震装置の検査データ改ざん事件である。“他山の石”とすべき東洋ゴムの不正を知りながら、この3年間、KYBはヒヤヒヤすることもなく不正を繰り返していたのだろうか。
これまで、直接的に関わった現場の品質検査要員は8人ほどで交代してきて、新しい担当者が不正に気づいて改ざんが発覚したといわれるが、それまでは要員交代の都度、“手抜き”のノウハウを伝授してきたのだろうか。
不正の要因を探ればいろいろあり、要員不足もその1つであろうが、生産管理の3要素である原価・品質・納期管理の締め付けが、手抜きのできる品質管理にしわ寄せされたということでもあろう。
日本の製造業は、戦後の「安かろう悪かろう」の稚拙なモノ作りから始まった。アメリカの「科学的管理法」や「統計的品質管理」など、生産の思想や管理技法を学びながらモノづくりに励み、世界に誇る高品質の製品を生み出すところまで成長してきた。
さらにその現場には、昭和40年代を中心とする全盛期の品質管理があった。そして、「QC(品質管理)サークル」による自主的な改善活動が活発だった。この小集団活動が品質向上に大きな役割を果たした。現場の作業員が熱心に製造現場の問題点を探り、改善案を検討し合っていたから、問題点や不正を隠すということはなかった。
それに比べて現代は、長年かけて業務に精通していく終身雇用制もない。社員の自己啓発マインドも低下しがちである。不正規社員や中途採用社員が増えている。働き過ぎは罪悪、残業規制優先である。世界に例のない純日本的な自主活動のQCサークルなどは流行らない時代になった。
かくして、いいものを作れば売れると信じて「オーバースペック」になってもそれを誇りにしてきた日本の製造業が、企業の命である製品の品質を削ぎ落しはじめたのは、バブル景気がはじけた90年代以降ではなかろうか。
QC全盛時の現場には、不正を除去する「透明性」があった。いまさら昔に帰るすべもないが、不正防止に限って言えば、やはり現場の透明性とモラル、現場と中間管理職と経営陣をつなぐ情報伝達の建て直しだろう。
本来日本の強みであったはずの現場に始まる組織内の「透明化」をいかに取り戻すか。結局、データ管理や情報管理や、企業ガバナンスなど管理技法やシステムの問題より、人間関係と組織の透明性を向上させることが、不正防止の決め手ではないか。
(山勘 2018年11月20日)
言うまでもないことだが、「労働力」は機械的なパワーではない。人間の肉体に内在するパワーだ。したがって外国人「労働力」の受け入れを拡大するということは、とりもなおさず生身の「外国人」の受け入れを拡大するということだ。
ここで「移民政策」の是非を性急に問うつもりはないが、その「移民政策」に密接に関連する外国人労働力の流入拡大は、遅かれ早かれ我が国の「多民政策」の在り方が問われ、近い将来に、欧米の移民問題の苦難を日本も直面し、日本の国のかたちを変える方向に向かう大問題だ。
10月30日の新聞各紙は、この臨時国会で、入管法改正を巡る論戦開始を報じる一方で、独メルケル首相の与党党首辞任表明を同時に伝えた。メルケル氏は、首相職については任期の21年まで続投するという。メルケル氏は、反トランプで欧州をリードしてきたリベラルの旗手だ。そのメルケル氏を党首辞任に追い込んだ国内的な人気低迷は、100万人超の難民を受け入れた「移民政策」が大きな原因だ。
一方わが国では今、臨時国会が始まり、安倍内閣による外国人労働力の受け入れ拡大に向けた入管法改正案が注目されている。質問に立った立憲民主党の枝野幸男代表は、安倍首相に対して、「これまで首相自身が否定してきた移民受け入れ政策への転換とどう違うのか」と質した。
これに対して安倍首相は、入管法改正は移民政策ではないとして、「一定規模の外国人と家族を、期限を設けることなく受け入れて国家を維持しようという移民政策は採らない」と従来通りの答弁を繰り返した。
枝野氏は、外国人労働者のための、職場環境、日本語教育、住宅問題、社会保障などの課題をあげ、国民民主党玉木雄一郎代表は、外国人と共生できる社会づくりをあげたが、首相は移民政策への転換には当たらないと強調するだけで、受け入れ体制の具体案には一言も触れなかった。
要するに、安倍首相の、「移民政策は採らない」という意味は、移民受け入れではない、受け入れるのは難民、移民ではない単なる「労働力」だということらしい。しかし、難民、移民ではないにしても、移入労働力の拡大でやってくるのは、体温を持たない無機質の「労働力」ではない。「労働力」を背負ってくるのは「人間」だ。
労働力としてやってくる人間、労働者の移入拡大は、野党の主張する受け入れ政策の整備を必要とする。さらには、移民政策との兼ね合いも、そして実質的な移民受け入れによって変容する将来の国のかたちまで考えて論議すべきだろう。
(山勘 2018年11月20日)